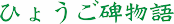- 北野浄水構場の碑(神戸市中央区北野町)
-
 水道の民営化に道を開く水道法が「改正」されたのを機に、改めてライフラインとしての水道が注目されている。
水道の民営化に道を開く水道法が「改正」されたのを機に、改めてライフラインとしての水道が注目されている。
神戸の水道は、この国の都市水道としては7番目の近代水道として1900年(明治33年)に給水を開始した。水道敷設のきっかけとなったのは、神戸港の開港で人口が急増したことだ。インフラ整備が伴わず、不衛生な井戸水の使用でコレラなど伝染病が頻発したことが水道敷設の機運を高めた。
布引谷と烏原谷が水源に選ばれ、最初に布引から奥平野浄水場(兵庫区楠谷町)へ導水管が敷設された。写真の右手にある黒い筒状のものが2009年まで埋設されていたイギリス製の導水管(直径60㌢、鋳物製)の一部である。
このときの計画給水は生田川と湊川の間(旧生田区のほぼ全域)、25万人であった。神戸市全域に給水がいきわたったのは、戦災や水害などを挟んだ1985年という。
現在の神戸の水源は、その約7割強が琵琶湖・淀川の水で、自己水源は布引、烏原のほかに千刈貯水池や新神戸トンネルの湧水などだ。
【メモ】神戸市中央区北野町1丁目。異人館街の東端にある北野三本松広場から東へすぐ。
(鍋島) 写真:新神戸駅から北野方面に少し進んだところに浄水場があった
2019年3月12日号
|
 水道の民営化に道を開く水道法が「改正」されたのを機に、改めてライフラインとしての水道が注目されている。
水道の民営化に道を開く水道法が「改正」されたのを機に、改めてライフラインとしての水道が注目されている。