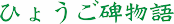- 大鳥圭介の碑(赤穂郡上郡町)
-
 日本近代化のパイオニアと言われる大鳥圭介は、1832(天保3)年、赤穂郡細念村(現在の赤穂郡上郡町)で、代々村医者を務めている大鳥家の長男として生まれた。
日本近代化のパイオニアと言われる大鳥圭介は、1832(天保3)年、赤穂郡細念村(現在の赤穂郡上郡町)で、代々村医者を務めている大鳥家の長男として生まれた。
岡山の閑谷学校で漢学、儒学、漢方医学を学んだ後、家業を継ぐべく修行をしていたが、蘭学に興味を持ち、大坂の適塾で蘭学と西洋医学を、また、江戸の大木塾で医学、兵学、工学を、その他、軍学、写真術、英語なども学び、江戸の江川塾に招かれて教授となった。
やがて江戸幕府に登用され歩兵奉行に抜擢された。大政奉還後の戊辰戦争では土方歳三や榎本武揚らとともに各地で新政府軍相手に徹底抗戦を行ったが、最後には函館の五稜郭で降伏した。
しかし、大鳥圭介は「やることは十分やったから降参した。死ぬことはない」と一転、明治新政府の要職に就き、日本の殖産興業に尽力、清国、朝鮮国公使としても活躍した。
中年以上の御仁にとっては「おおとりけいすけ」と言えば、あの「ポテチン」で有名な漫才師の鳳啓助が頭に浮かぶであろうが、実は無関係ではない。旅回り一座だった小田啓三少年がやっと舞台に上がれた時、かねてから敬服していた偉人の名前をもじって芸名としたのだ。
上郡町役場の玄関口には大鳥圭介の立像があり、生家跡には生誕地の碑も建てられている。
【メモ】上郡町役場へはJR山陽本線・上郡駅から徒歩約25分。生家跡(上郡町岩木丙)へは町役場から車で北へ約5分。
|
 日本近代化のパイオニアと言われる大鳥圭介は、1832(天保3)年、赤穂郡細念村(現在の赤穂郡上郡町)で、代々村医者を務めている大鳥家の長男として生まれた。
日本近代化のパイオニアと言われる大鳥圭介は、1832(天保3)年、赤穂郡細念村(現在の赤穂郡上郡町)で、代々村医者を務めている大鳥家の長男として生まれた。