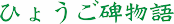- 馬車道修築の碑(姫路市)
-
 奈良時代、天皇の命により各国別の「風土記」が編纂された時、「郡郷の名に好字をつけること」との条件があったため、中国山地の分水嶺にあった「死野(しにの)」と呼ばれていた地は、一転、「生野」に変えられたと言う。
奈良時代、天皇の命により各国別の「風土記」が編纂された時、「郡郷の名に好字をつけること」との条件があったため、中国山地の分水嶺にあった「死野(しにの)」と呼ばれていた地は、一転、「生野」に変えられたと言う。
播磨風土記によると、この辺りには荒ぶる神がいて、往来する人の半分の命を奪われるから「死野」と言う、とあるが、これは、鉱毒が原因ではないかとの説がある。
生野で銀鉱が開坑されたのは1542年(天文11年)とされているが、精錬技術の発達により産銀量も増加。多くの新しい鉱脈も発見され、「銀鉱旧記」には「此等の間歩より銀出る事、恰も土砂の如し」との記述があるほどの盛況ぶりだった。
明治になって外国の技術も取り入れ、銀鉱の近代化が取り組まれてさらに増産。生野から飾磨港(現姫路港)までの全長49㎞(周辺の鉱山群も入れると73㎞)の「銀の馬車道」が建設される。この道路は、日本で最初の「舗装」という概念を持つ高速産業道路であり、1876年(明治9年)に完成。これを記念して、最も難工事だった藪田橋(現・生野橋。写真の背景の橋)のたもとに碑が建てられた。1895年(明治28年)播但鉄道(現・JR播但線)が開通し、「銀の馬車道」はその役目を終えた。
【メモ】神姫バス姫路駅から北条行きで約25分、生野橋停留所下車。徒歩5分
|
 奈良時代、天皇の命により各国別の「風土記」が編纂された時、「郡郷の名に好字をつけること」との条件があったため、中国山地の分水嶺にあった「死野(しにの)」と呼ばれていた地は、一転、「生野」に変えられたと言う。
奈良時代、天皇の命により各国別の「風土記」が編纂された時、「郡郷の名に好字をつけること」との条件があったため、中国山地の分水嶺にあった「死野(しにの)」と呼ばれていた地は、一転、「生野」に変えられたと言う。