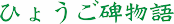- 寛延義民の碑(姫路市夢前町)
-
 寛延2(1749)年、姫路藩で百姓大一揆が勃発した。この頃、姫路藩は、陸奥白河から極端な赤字財政の松平明矩(あきのり)が転じ、相次ぐ凶作にもかかわらず、厳しい年貢の取立てを行っていた。百姓たちは、生活の窮状を訴え、藩に対して度々年貢の減免や猶予を願い出たが認められず、ついに、領内のあちこちで蜂起が始まる。
寛延2(1749)年、姫路藩で百姓大一揆が勃発した。この頃、姫路藩は、陸奥白河から極端な赤字財政の松平明矩(あきのり)が転じ、相次ぐ凶作にもかかわらず、厳しい年貢の取立てを行っていた。百姓たちは、生活の窮状を訴え、藩に対して度々年貢の減免や猶予を願い出たが認められず、ついに、領内のあちこちで蜂起が始まる。
姫路の北の置塩(おきしお)村でも滑(なめら)の甚兵衛をはじめ、塩田の利兵衛、又坂の与次右衛門を指導者として、庄屋の打ち壊し、焼き討ちが始まり、やがて、加古郡印南の一揆とも合流して、総勢1万人余の大一揆となった。もはや姫路藩だけでは対処できず、大坂奉行所の応援を得てようやく鎮圧された。
この一揆で、滑の甚兵衛ら345人が捕えられ、磔、獄門、遠島、追放などの重刑に処せられた。時に、甚兵衛40歳、利兵衛37歳、与次右衛門32歳であった。
地元では彼らを「寛延義民」と称え、置塩神社に祀っている。
置塩神社は、姫路市夢前町の塩田温泉にあり、境内には八女から石を取り寄せ、「義民の会」による灯篭100基が立ち並んでいる。鳥居には「寛延義民社」と掲げられ、鳥居の下の「寛延義民顕彰会」の碑には「尊い志は、未来永劫に郷土の誇りとして伝えたい」とある。
|
 寛延2(1749)年、姫路藩で百姓大一揆が勃発した。この頃、姫路藩は、陸奥白河から極端な赤字財政の松平明矩(あきのり)が転じ、相次ぐ凶作にもかかわらず、厳しい年貢の取立てを行っていた。百姓たちは、生活の窮状を訴え、藩に対して度々年貢の減免や猶予を願い出たが認められず、ついに、領内のあちこちで蜂起が始まる。
寛延2(1749)年、姫路藩で百姓大一揆が勃発した。この頃、姫路藩は、陸奥白河から極端な赤字財政の松平明矩(あきのり)が転じ、相次ぐ凶作にもかかわらず、厳しい年貢の取立てを行っていた。百姓たちは、生活の窮状を訴え、藩に対して度々年貢の減免や猶予を願い出たが認められず、ついに、領内のあちこちで蜂起が始まる。