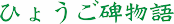- 中村大佐顕彰碑(姫路市)
-
 明治になって全国の城郭は無用の長物となり、1873(明治6)年、陸軍が兵営地や訓練場として価値を認めた43城以外は「廃城令」によりすべて取り壊された。姫路城は、その43城の中に残ったが、あくまでも必要なのは軍事的に利用ができる敷地であり、城そのものの歴史的、文化的価値を認めるという発想はなく、かといって、解体には莫大な費用がかかるため、城は放置され、荒れるに任されていた。
明治になって全国の城郭は無用の長物となり、1873(明治6)年、陸軍が兵営地や訓練場として価値を認めた43城以外は「廃城令」によりすべて取り壊された。姫路城は、その43城の中に残ったが、あくまでも必要なのは軍事的に利用ができる敷地であり、城そのものの歴史的、文化的価値を認めるという発想はなく、かといって、解体には莫大な費用がかかるため、城は放置され、荒れるに任されていた。
しかし、1878年ごろになると、荒れるのも限界となり、いよいよ取り壊しの話が持ち上がってくる。その時、陸軍省で陸軍の建築、修繕を担当する第4局の局長代理であった中村重遠(しげとお)大佐が、全国の城を視察する中で、特に姫路城と名古屋城に文化的価値を見出し、時の陸軍卿山縣有朋に、この2城を残すよう意見書を提出した。やがて、陸軍参謀本部がこの上申を認めたため、応急の保存工事が国の予算で行われることになり、後の大修理へとつながっていく。
この中村大佐の功績をたたえ、姫路城に入場してすぐ目の前の「菱の門」の近くに「中村大佐顕彰碑」が建てられている。
播州段文音頭の一節にも登場する中村大佐であるが、なぜかこの碑に注目する人は少ない。
写真:姫路城内の「菱の門」近くに建てられているこの碑に注目する人はなぜか少ない
|
 明治になって全国の城郭は無用の長物となり、1873(明治6)年、陸軍が兵営地や訓練場として価値を認めた43城以外は「廃城令」によりすべて取り壊された。姫路城は、その43城の中に残ったが、あくまでも必要なのは軍事的に利用ができる敷地であり、城そのものの歴史的、文化的価値を認めるという発想はなく、かといって、解体には莫大な費用がかかるため、城は放置され、荒れるに任されていた。
明治になって全国の城郭は無用の長物となり、1873(明治6)年、陸軍が兵営地や訓練場として価値を認めた43城以外は「廃城令」によりすべて取り壊された。姫路城は、その43城の中に残ったが、あくまでも必要なのは軍事的に利用ができる敷地であり、城そのものの歴史的、文化的価値を認めるという発想はなく、かといって、解体には莫大な費用がかかるため、城は放置され、荒れるに任されていた。