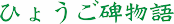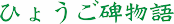
- 三木清レリーフと歌碑(たつの市)
-
 三木清は、1897(明治30)年、たつの市揖西町小神(いっさいちょうおがみ)に生まれる。第一高等学校時代に、西田幾多郎の『善の研究』に強い感銘を受け、京都大学の哲学科に進む。3年間のドイツ留学でハイデッガーに学び、1925(大正14)年、帰国して『パスカルに於ける人間の研究』を出版した。
三木清は、1897(明治30)年、たつの市揖西町小神(いっさいちょうおがみ)に生まれる。第一高等学校時代に、西田幾多郎の『善の研究』に強い感銘を受け、京都大学の哲学科に進む。3年間のドイツ留学でハイデッガーに学び、1925(大正14)年、帰国して『パスカルに於ける人間の研究』を出版した。
1927(昭和②)年、法政大学の哲学科教授に赴任、人間学を基礎とした三木独自のマルクス解釈を展開し始める。1930(昭和5)年、日本共産党への資金援助の嫌疑で検挙・拘留され執行猶予となるが、その後は一切の教職から身を引き民間の哲学者を通した。
1939(昭和14)年に出版した『人生論ノート』『哲学ノート』は、戦地に赴く若き学徒の鎮魂の書として愛読されたという。三木は、近衛文麿の政策集団である「昭和研究会」にも加わり、大東亜共同体論を展開するが、その思想さえ左寄りと見られる局面に突き進んでいく。
敗戦の年の1945(昭和20)年3月、旧友である脱走した共産党員に食事と衣服を与えたとして治安維持法により投獄。9月26日、豊多摩拘置所で疥癬の悪化により獄死。49歳だった。
【メモ】碑は、たつの市の国民宿舎「赤とんぼ荘」から続く「哲学の小径」沿いに三木の故郷、揖西町小神を見下ろす形で佇む。
写真:碑は国民宿舎「赤とんぼ荘」から続く「哲学の小径」沿いに立つ
(森山容光)
ミュージアムを終えて
100回を越えたのを機に、「ひょうごミュージアムめぐり」を終えた。2009年1月から始め、100回に到達するのに6年を要した。
ミュージアム=博物館は、歴史・美術・自然史・科学・郷土資料・動植物など多岐にわたる。およそ人間にかかわりのある分野が何らかの形で記録・保存・調査・研究され、その価値を明らかにし、今に伝えている。それらは人びとの労働と暮らしと切り離すことのできないものであり、未来につなぐ意味からもミュージアムの果たす役割は大きい。
ところで、「学芸員はガンだ」と発言した大臣がいたが、学芸員なくして博物館の維持・運営はできない。正規のスタッフを増員することが先決ではないか。博物館の多くはアウトソーシングされ、予算削減で人員の確保が十分にできず、資料収集や保存・調査・研究に支障をきたしている。安倍政権が求める博物館の「観光資源化」は本末転倒で看過できない。
政府の浅はかさに対し、約4千の博物館が加盟する日本博物館協会では、「歴史と向き合う博物館―博物館が語るもの」をテーマに、博物館が果たす社会的役割についてキャンペーン中だ。
この問題は、国および自治体の責務であり、私たちも連動して施策の充実をめざし取り組まねばならない課題である。 鍋島浩一
2017年5月23日号
|
 三木清は、1897(明治30)年、たつの市揖西町小神(いっさいちょうおがみ)に生まれる。第一高等学校時代に、西田幾多郎の『善の研究』に強い感銘を受け、京都大学の哲学科に進む。3年間のドイツ留学でハイデッガーに学び、1925(大正14)年、帰国して『パスカルに於ける人間の研究』を出版した。
三木清は、1897(明治30)年、たつの市揖西町小神(いっさいちょうおがみ)に生まれる。第一高等学校時代に、西田幾多郎の『善の研究』に強い感銘を受け、京都大学の哲学科に進む。3年間のドイツ留学でハイデッガーに学び、1925(大正14)年、帰国して『パスカルに於ける人間の研究』を出版した。