- 篠山城跡 (篠山市)
-
 前回の立杭の郷から足を延ばし、篠山市の中心、篠山城跡を訪ねる。
前回の立杭の郷から足を延ばし、篠山市の中心、篠山城跡を訪ねる。
篠山城は、徳川家康が西国大名を抑えるため山陰道の要衝である丹波篠山盆地に造らせた平山城だが、城郭が堅固すぎるとして天守閣は造られなかった。明治になって廃城令で城郭の建造物は取り壊されていくなか、二の丸の大書院だけが保存のため残されていたが、1944(昭和19)年に失火で焼失し、2000年に再建されて城郭の名残りを留めている。この大書院は、のびやかな曲線の屋根を持つ京都二条城に極似の壮大な規模の木造建築物で、外からはその優美な曲線の屋根だけが堀の石垣の上にわずかに見えるのみ。
外濠と内濠の間にある三の丸の駐車場に車を置き城跡に入って行くと、鉄門跡、大書院入館口を経て二の丸庭園に出る。庭園の広い地面に礎石が配置され、城郭の間取りが再現され、案内板が埋め込まれている。この広場の東隅の本丸跡に城主青山家を祀る青山神社が建てられていて、その奥に20㍍四方ほどの天守台がある。そこからは眼下に城下町の町並み、はるかに丹波富士が望まれる。内濠と外濠沿いの桜並木が春の到来を待っている。
(嶋谷)
2014年1月21日号
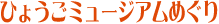
- 柳田國男・松岡家記念館 (神崎郡福崎町西田原)
-
 福崎町は中国道と播但道が交差する一帯に位置する。その福崎インターの西北、役場の北に記念館がある。
福崎町は中国道と播但道が交差する一帯に位置する。その福崎インターの西北、役場の北に記念館がある。
日本民俗学の先駆け、柳田國男は1875(明治8)年、松岡家の六男として福崎で生まれた。記念館は、柳田をはじめ松岡鼎(医師)、井上通泰(国文学者・歌人)、松岡静雄(言語学者)、松岡映丘(日本画家)の兄弟を顕彰して設立された。その記念館横には、柳田が著書『故郷70年』で「日本一小さな家」といい「そこから民俗学への志しも源を発したといってよい」と述べた生家が移築され保存されている。
農務省を45歳で退官し日本列島の調査旅行がスタートするのだが、そのきっかけとなったのが宮崎県椎葉村を訪ねたことである。著名な『遠野物語』より3年前に発表された『後狩詞記』で焼畑やこれにまつわる独特の風習・儀礼を紹介した。
三男の通泰は、國男に勧められて『播磨風土記』に出てくる地名の研究に取り組み、『播磨風土記新考』を著した。
★神崎郡福崎町西田原1038―12 電話0790―22―1000。JR播但線・福崎駅から巡回バスで、もちむぎのやかた下車。開館は9時から16時30分。月曜休館。無料。
写真:日本民俗学の先駆け柳田國男とその兄弟たち(医師、国文学者、言語学者、日本画家)を顕彰
2014年1月21日号
|
 前回の立杭の郷から足を延ばし、篠山市の中心、篠山城跡を訪ねる。
前回の立杭の郷から足を延ばし、篠山市の中心、篠山城跡を訪ねる。
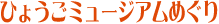








 福崎町は中国道と播但道が交差する一帯に位置する。その福崎インターの西北、役場の北に記念館がある。
福崎町は中国道と播但道が交差する一帯に位置する。その福崎インターの西北、役場の北に記念館がある。