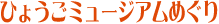- 多可町立杉原紙研究所 (多可郡多可町加美区)
-
 西脇を出て中町から国道427号線を北上し、青垣への峠にさしかかると三国岳が迫ってくる。その急峻な山間の杉原谷に研究所がある。
西脇を出て中町から国道427号線を北上し、青垣への峠にさしかかると三国岳が迫ってくる。その急峻な山間の杉原谷に研究所がある。
この地の紙漉は、737(天平9)年の『正倉院文書』に初見されることから、1300年の歴史を持つ。夏も冷涼で原料の楮(こうぞ)が豊富に自生し、三国岳からわき出る澄んだ水が紙漉に適した。
平安時代は貴族の贈答品、献上品として使われる。室町期から庶民の日常生活にも広がり、江戸中期以降は杉原谷の業者は300軒を超えた。けれども明治になると洋紙に圧倒され、大正末には伝統の技法が途絶える。
復活するのは50年後の1972年である。和紙研究の第一人者である寿岳文章氏の調査研究がその契機となった。その縁で10年前には『寿岳文庫』が併設されている。ちなみに、女性問題や護憲運動に取り組んだ娘の寿岳章子氏は研究所の名誉館長を務めた。
杉原紙は、雪降る厳冬期の「川さらし」があって、心和む和紙となる。
★多可郡多可町加美区鳥羽768-46 電話0795-36-0080。JR西脇駅から神姫バス「杉原紙研究所」下車。開館は8時30分から17時。水曜休館。入館料=無料。
写真:1300年の歴史を持つ杉原紙は大正末には伝統の技法が一度途絶えるが、1972年に復活した
2011年10月11日号
|
 西脇を出て中町から国道427号線を北上し、青垣への峠にさしかかると三国岳が迫ってくる。その急峻な山間の杉原谷に研究所がある。
西脇を出て中町から国道427号線を北上し、青垣への峠にさしかかると三国岳が迫ってくる。その急峻な山間の杉原谷に研究所がある。