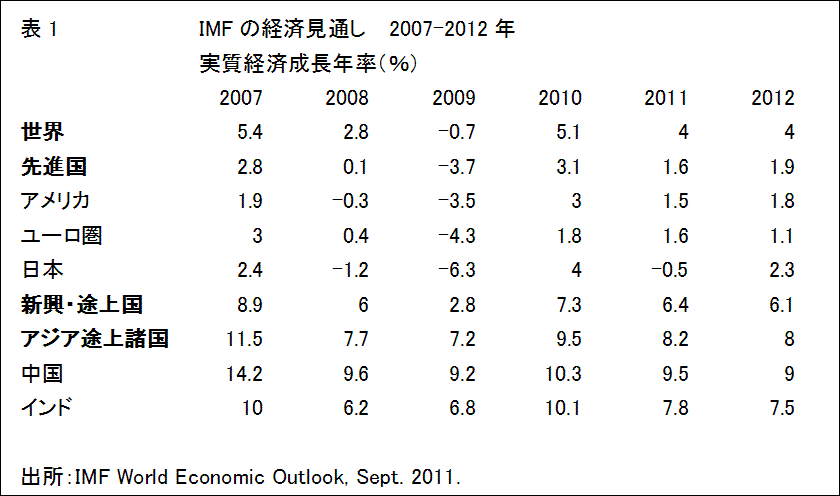「新社会兵庫」 2月14日号 「新社会兵庫」 2月14日号
- 篠山での講演会に380人
-
 「ひょうご丹波・憲法を生かす会」と「憲法たんば」(平和憲法を守る丹波連絡会)は1月26日、篠山市民センターで京都大学原子炉実験所助教の小出裕章さんを講師に招き、「原発のウソと真実」と題する講演会を開いた(篠山市、篠山市教育委員会、神戸新聞社、丹波新聞社が後援)。会場を超満員にする380人が参加し、福島原発事故や放射能汚染の実情、その事故が問いかける人間の生き方などについて1時間半にわたって語った小出さんの講演に聴き入った。
「ひょうご丹波・憲法を生かす会」と「憲法たんば」(平和憲法を守る丹波連絡会)は1月26日、篠山市民センターで京都大学原子炉実験所助教の小出裕章さんを講師に招き、「原発のウソと真実」と題する講演会を開いた(篠山市、篠山市教育委員会、神戸新聞社、丹波新聞社が後援)。会場を超満員にする380人が参加し、福島原発事故や放射能汚染の実情、その事故が問いかける人間の生き方などについて1時間半にわたって語った小出さんの講演に聴き入った。
 小出さんは一貫して原発の危険性を訴え、各地の反原発闘争にも関わってきた研究者。福島原発事故後は、研究の傍ら休日なしで講演などのために全国を駆け回る超多忙な日々を送っており、今回の日程は昨年4月に依頼して決まったもの。そんな小出さんの講演への関心は高く、参加者は県内各地から集まった。
小出さんは一貫して原発の危険性を訴え、各地の反原発闘争にも関わってきた研究者。福島原発事故後は、研究の傍ら休日なしで講演などのために全国を駆け回る超多忙な日々を送っており、今回の日程は昨年4月に依頼して決まったもの。そんな小出さんの講演への関心は高く、参加者は県内各地から集まった。
小出さんは、「いま、戦争でも起きないようなことが起きている」として福島原発事故による悲劇の実情に触れ、この悲劇を引き起こした放射能について、今回の事故で広島に落とされた原爆の170発分のセシウム137が大気中に放出されたことを明らかにした。しかも、放射線管理区域並みの地域が関東にまで広がっており、「土地も食べ物も、すべてが放射性物質になってしまった。放射能で汚れた世界で生きるしかない」と指摘。「この悲劇は東電が何回倒産しても購いきれるものではない」、「きっと私たちは未来の子どもたちから『その時、どう生きていたのか』と問われるだろう」と述べた。また、「事故の責任は東電、原発を推進してきた政治家、学者にある。そして原子力の研究の場にいる私にもある。しかし、54基もの原発をつくってしまった日本に生きてきたすべての大人にも責任があるのでは」とも述べた。そして、「私の願いは、原子力を選んだことに何の責任もない子どもたちを被曝させないこと。食品の汚染の度合いを徹底的に調べ、汚染の少ないものを子どもに与え、高いものは大人が食べるしかない。そういう世界になってしまったのだ」とつないだ。
最後に、「Nuclear」を「核」と「原子力」で使い分けているが、原発と核兵器は一体のものであることを、日本政府の見解を紹介しながらあらためて指摘し、憲法9条の重さにも言及した。
講演と質疑を収録したDVDが頒布中(300円)。問合せは「憲法たんば」事務局へ。電話0795‐73‐3869
写真上:会場が超満員となった小出裕章さんの「原発のウソと真実」と題した講演会=1月26日、篠山市
静かな語り口で熱い思いを訴える小出裕章さん=1月26日
- 日米共同演習に抗議行動 1.22 伊丹市
 陸上自衛隊と米陸軍による「日米共同指揮所演習」(ヤマサクラ61)が、陸自中部方面総監部がある伊丹駐屯地を主会場に1月31日から2月5日まで行なわれた。
ヤマサクラはコンピューター・シミュレーションによる図上演習で、今回が61回目。伊丹駐屯地では00年、07年につづき3回目。陸上自衛隊約4500人、米軍約1500人のほか、オーストラリア陸軍も初のオブ参加、ソウルの在韓米陸軍も初参加して演習の指揮にあたったとされる。一時明らかになったシナリオは、中国、北朝鮮の連合軍が日本を侵略したと想定、これを撃破するというものである。
陸上自衛隊と米陸軍による「日米共同指揮所演習」(ヤマサクラ61)が、陸自中部方面総監部がある伊丹駐屯地を主会場に1月31日から2月5日まで行なわれた。
ヤマサクラはコンピューター・シミュレーションによる図上演習で、今回が61回目。伊丹駐屯地では00年、07年につづき3回目。陸上自衛隊約4500人、米軍約1500人のほか、オーストラリア陸軍も初のオブ参加、ソウルの在韓米陸軍も初参加して演習の指揮にあたったとされる。一時明らかになったシナリオは、中国、北朝鮮の連合軍が日本を侵略したと想定、これを撃破するというものである。
共同演習に先立つ1月22日、「ストップ!ヤマサクラ61大集会」(同実行委員会主催)が伊丹市・昆陽池公園で開かれ、近畿各地から約800人が参加した。
集会では、社民党、共産党、新社会党の政党代表があいさつに立ち、新社会党からは小林るみ子神戸市議があいさつした。連帯の訴えとして、沖縄・名護市からかけつけた「ヘリ基地反対協」共同代表、比嘉靖さんが登壇し、普天間基地即時閉鎖、辺野古への新基地建設阻止を訴えた。賛同議員のアピールなどの紹介のあと、「怒」と書かれたプラカードを参加者が一斉に掲げることで集会アピールを採択した。
集会後はデモ行進に出発。陸上自衛隊第三師団の西門前を通り、中部総監部を取り囲むヒューマンチェーンに取り組んだ。
写真:参加者は「怒」と書いたプラカードを掲げて日米共同演習に抗議する集会アピールを採択した=1月22日、伊丹市昆陽池公園
- 借り上げ復興公営住宅の返還問題でシンポジウム開催 1.14 神戸
-
 阪神・淡路大震災17年を前に、被災者向けに県や神戸市などがUR(都市再生機構)など民間から借り上げた復興公営住宅の返還問題についてのシンポジウムが1月14日、神戸市内で開かれた。「食い止めよう!『借り上げ公営住宅』からの追い出し」と掲げ、「被災地と被災者を考える懇談会」が主催したもので、約100人が参加した。
阪神・淡路大震災17年を前に、被災者向けに県や神戸市などがUR(都市再生機構)など民間から借り上げた復興公営住宅の返還問題についてのシンポジウムが1月14日、神戸市内で開かれた。「食い止めよう!『借り上げ公営住宅』からの追い出し」と掲げ、「被災地と被災者を考える懇談会」が主催したもので、約100人が参加した。
借り上げ住宅は県内に約6600戸あるが、県や神戸市は20年の契約期間が終わるという理由で、早い住宅では2015年からの転居を居住者に迫っている。
シンポジウムでは、住宅入居者として山村ちずえさん、吉山隆生さん、安田秋成さんが発言。マスコミの立場から神戸新聞の岸本達也記者、UR団地自治会長の立場から神戸市議の粟原富夫さん、国会でこの問題に取り組んでいる服部良一衆議院議員、さらに関西学院大教授の室崎益輝さんがそれぞれ発言した。
この中で山村さんは「転居の通知が来て精神的に悩んでいる人もいる。でもみんなで一緒に頑張ろうと入居継続の署名も半分の人から集まっている」。また、安田さんは「高齢者同士のつながりを築くのは難しく、10年でやっと築けた。これを断つのは高齢者を孤立に追い込み、まさに人災だ」と現状を訴えた。粟原さんは「団地で被災者同士の交流などを重ねてようやく自治会として署名運動に取り組めるようになった。今後も自治会として支えていきたい」と訴え、室崎さんは「仕事や土地、人やくらしのつながりから、そこにしか住めない人がいる。居住の権利として、この問題で神戸が今後どうなるか、東日本にもつながる問題だ。行政は住民と一緒にもっと知恵を出し合うべきだ」と指摘した。
シンポジウムではこのほか、「神戸の実態を国連社会権規約委員会に出すべき」「裁判にも訴えるべき」などの意見が出された。
主催した「被災地と被災者を考える懇談会」では現在居住継続を求める署名運動を展開中で、2月中にも自治体に提出する予定だ。(N)
写真:住宅入居者、自治会、マスコミ関係、学者などさまざまな立場から問題点を論じたシンポジウム=1月14日、神戸市
- 「憲法を生かす北区の会」と「憲法を生かす会・灘」がそれぞれ集いを開催
-
 「憲法を生かす北区の会」と「憲法を生かす会・灘」は、脱原発運動の一環として、原発事故による福島県からの避難者の思いを聴く集いをそれぞれ持った。
「憲法を生かす北区の会」と「憲法を生かす会・灘」は、脱原発運動の一環として、原発事故による福島県からの避難者の思いを聴く集いをそれぞれ持った。
神戸市北区では1月22日、北区民センターで開いた第21回憲法を考える集いで、灘区では27日に開いた六甲道勤労市民センターでの憲法サロンで、ともに原発事故前までは福島県南相馬市で農業を営んでいて、いま灘区に避難している水谷堯宣(みずがいたかのぶ)さん(74)のお話を聴いた。
水谷さんは、原発事故直後の、事態もよく知らされないまま混乱した状況のなかでの避難の実情から、避難後の賠償問題に関する東京電力や厚労省、地元自治体とのやりとりの問題点などを、悔しさを乗り越えるように語った。一瞬の原発事故によって、大切にしてきた土地、仕事、暮らし、そして故郷を奪われてしまい、心にも大きな痛手を負いながらも、「故郷を奪われてなるものか」とばかり、再び福島に戻って農業を再開したいという切実な思いを吐露した。
◇
水谷さんのインタビュー記事はバックナンバー(1月24日号)に収録。
写真:神戸市灘区に避難中の水谷堯宣さんが故郷に戻り農業を再開したいという思いを語った=1月27日、神戸市灘区
- 東日本大震災の被災地との連帯、借り上げ住宅の転居強制反対訴え
-
 今年で第17回目となる「1・17追悼・連帯・抗議の集い」が、阪神・淡路大震災から17年の1月17日、神戸市役所前で開かれた(主催は兵庫県被災者連絡会などでつくる実行委員会)。
今年で第17回目となる「1・17追悼・連帯・抗議の集い」が、阪神・淡路大震災から17年の1月17日、神戸市役所前で開かれた(主催は兵庫県被災者連絡会などでつくる実行委員会)。
東日本大震災の被災地・被災者との連帯が強く意識されるとともに、阪神・淡路大震災をめぐっては「『借り上げ復興住宅』の『明け渡し→転居』強制を許さない!」がスローガンに掲げられた。
各界からの連帯あいさつでは、新社会党神戸市議団からあわはら富夫市議があいさつに立ち、借り上げ復興住宅の転居問題について、「やっとできたコミュニティを破壊するもの。居住の延長措置をかちとろう」と訴えた=写真。
ステージではいつものように、「はるまきちまき」の歌のほか沖縄民謡やエイサーなど歌、演奏、舞踏が披露された。
会場には展示コーナーも設けられ、東日本大震災の被災地での支援活動などがパネルによって紹介されていた。
- ひょうご労働安全衛生センターらが募金活動の取り組み 1.17
 阪神・淡路大震災から17年を迎える1月17日、ひょうご労働安全衛生センターとアスベスト疾患・患者と家族の会のメンバーは神戸市三宮のフラワーロード周辺で、東日本大震災の被災地へアスベスト用マスクを届けるための募金活動を取り組んだ。
阪神・淡路大震災から17年を迎える1月17日、ひょうご労働安全衛生センターとアスベスト疾患・患者と家族の会のメンバーは神戸市三宮のフラワーロード周辺で、東日本大震災の被災地へアスベスト用マスクを届けるための募金活動を取り組んだ。
地震と津波により大量のガレキが発生した被災地では、ガレキの撤去、一時保管場所での作業に重機が用いられており、アスベストの飛散が危惧されている。そのため、将来、被災地でアスベストによる健康被害を発生させないため、昨年から街頭募金活動が取り組まれ、マスクを届ける活動が続けられている。
この日、メンバーらはマスク会社から提供を受けた防じんマスクを配布しながら、アスベストの危険性と専門のマスクの必要性を訴えた。黙って募金箱にお札を入れる人やベビーカーに乗った子どもの手から募金をしてくれる人もいたりして、32069円のカンパが寄せられた。
(N)
写真:ベビーカーに乗った子どもの手から募金してくれるひと幕も=1月17日、神戸市三宮
- 新社会党兵庫県本部が旗開き
 新社会党兵庫県本部の新年旗開き(「2012年新春のつどい」)が1月21日、神戸市中央区の兵庫県民会館で開かれ、党員、来賓、支援者ら約60人が参加した。党中央本部からは松枝佳宏委員長が参加し、服部良一衆議院議員(社民党)も激励に駆けつけた。
新社会党兵庫県本部の新年旗開き(「2012年新春のつどい」)が1月21日、神戸市中央区の兵庫県民会館で開かれ、党員、来賓、支援者ら約60人が参加した。党中央本部からは松枝佳宏委員長が参加し、服部良一衆議院議員(社民党)も激励に駆けつけた。
冒頭、主催者を代表して粟原富夫・兵庫県本部委員長があいさつ。「経済評論家の内橋克人さんが表現する〝うっぷん晴らし政治〟への渇望が、いま私の身近でも感じられる。橋下・大阪市長のような主張、やり方が〝貧困多数派〟の心に響いている。私たちはそれにどう反発、反撃するのか。まずは世の中の不利益を受けている彼らの受け皿になって支えなければならない」などと今年に臨む決意を述べた。
乾杯の後、来賓による連帯と激励のスピーチがつづき、ゲストパフォーマーとして招かれた神戸の歌姫・おーまきちまきさんとピアニスト・HALMA GENさんのユニット「はるまきちまき」による歌の演奏も行われ、つどいに華を添えた。党員有志による出し物も披露され、和やかな雰囲気の中、今年1年の躍進を誓って閉会した。
(彩)
写真:「“貧困多数派”に寄り添う運動を」と訴える粟原富夫・党兵庫県本部委員長=1月21日、兵庫県民会館
-
- 新社会党兵庫県本部が開いた公開講座(昨年12月3日)で、伊藤誠さん(東京大学名誉教授)が「世界経済の現状とTPPを考える」と題して講演された。以下はその要旨。
1.サブプライム世界恐慌から国家債務危機へ
2007年にアメリカに生じたサブプライム問題は08年9月のリーマン・ショックを介し、世界恐慌に拡大深化した。金融恐慌は実体経済に大きな打撃を与え、とくに先進諸国には国民総生産の大幅なマイナスが09年にかけて記録されている(表1)。
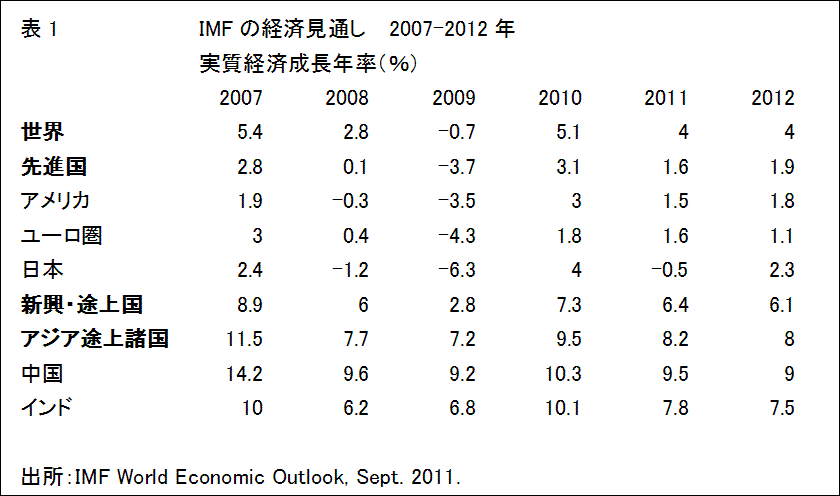
「100年に一度の大津波」といわれたこの世界恐慌は、1980年代以降、市場原理主義による民営化や規制緩和を推進したアメリカを中心とする新自由主義政策が、その中枢部にもたらした自壊作用によるものであった。
これに訂正を求める米日の民衆の選択が、09年の民主党への政権交代をもたらした。新たな発想に立った社会民主主義的政策への反転、たとえばグリーン・リカバリーやエコ・ポイント制、子ども手当などに期待が寄せられ、翌10年にかけての巨額な緊急経済対策とあわせて、かなりの幅での景気回復が先進諸国でも実現された。
しかし、この景気回復は、国家の債務危機を深化させつつ進行したので、やがて緊急経済対策の終了と緊縮政策への再帰がもたらされる。それに応じて、2011年には景気回復の鈍化や反落が予想されていた。
その予想は、想定外の規模で、世界経済危機を再現しつつある。まず、ユーロ圏でのギリシャ、イタリア、スペインなどの国家債務危機の深化、それらの国債の暴落、政変などが、ユーロ圏の政治経済を大きく動揺させ、ユーロの下落を生じつつある。ユーロ圏内の金融危機への再転化も一部に現実化しつつあり、それを防ぐための域内支援は、緊縮政策による財政再建を前提条件としているので、公務員の削減や給与のカットなどが、国家債務危機当事国から諸国に広がりやすい。
アメリカのオバマ政権も2011年夏、国家債務危機から財政運営に行き詰まる事態を迎え、共和党と妥協していっそうの緊縮政策に向かわざるをえなかった。その間にドルの信認も低下してドル安をもたらしている。しかもその間、金融諸機関への救済融資や公的資金の投入、法人税軽減や富裕層への優遇税制の温存や強化など、民主党も結局、「ウォールストリートの党」としての一面を脱していない、という失望感を民衆に与えつつある。
こうして、サブプライム世界恐慌は、国家債務危機の深化を経て、新自由主義的緊縮政策への反転をもたらしつつある。それは何を意味するか。現代世界のなかでのケインズ主義や社会民主主義の新たな回帰や定着はなぜ困難なのか。①資本主義のグローバリゼーションの定着、②中国、インドの工業化をふくむ産業基盤の移動、③サブプライム世界恐慌の深刻さ、不良債務問題のたらい回し的存続、などの諸側面にわたり、さらに検討を要するところがあろう。
2.大震災とTPP問題も加わった日本経済の激震
日本経済は、主要先進諸国のなかで、サブプライム恐慌の打撃を最も深刻に受けた。金融恐慌は比較的軽かったのに、実体経済面での影響が大きかったのはなぜか。それは先行の経済回復が、国内的に脆弱なまま、輸出拡大にのみ依存しがちであったためとみてよい。というのも、日本経済は、臨調行革以来の新自由主義のもとで、労働運動の弱体化、賃金の抑制、非正規の、とくに女性労働者の大量動員、少子化・高齢化の急速な進展、産業空洞化傾向、国家債務の累積などの問題を構造的に深化させ、将来不安を増し、内需を回復させにくい状況にあったためである。
民主党政権のもとでのエコ・ポイント制や子ども手当などの新たな発想による社会民主主義への期待感をふくめ、一時景気回復に向かった日本経済は、他の先進諸国と歩調を合わせるように、国家債務の増大への懸念から、それらの政策を2010年末以降、順次期限切れや減額・手直しや、廃止する方向に転じてゆく。それは民衆の失望を買うとともに、景気の再下降と反転を予測させる事態でもあった。
2011年3月11日の東日本大震災とそれに連動して生じた原発事故は、想定外の大打撃を日本経済に加えている。地震と津波による住宅、工場、道路などの資産への直接被害額のみでも16~25兆円と推定され、部品等のサプライチェーン寸断による産業活動の全国的低下、原発事故のための節電による経済活動の下向、自粛ムードによる消費需要の収縮などが合わさり、日本経済はこの年マイナス成長に再下降を迫られている。
雇用情勢や就職難問題にも厳しさが増している。大震災と原発事故への復旧・復興対策費は10年間で23兆円を要すると見込まれ、それに向けての増税案が検討されつつある。法人税の引き下げ案を取りやめれば10年間で15兆円程度は補えるという試算もあるが、その幅はせいぜい2~3年程度にとどめられそうである。
そのうえ、2011年夏以降のユーロ安、ドル安による円高が、日本経済に厳しい重圧を加えることとなっている。
こうした厳しい経済情勢のなかで、TPP(環太平洋連携協定)への参加の是非が、いま与野党をつうじて、大きな政治焦点となりつつある。
TPPは、2006年にAPEC(アジア太平洋経済協力会議)加盟国であるシンガポール、ニュージーランド、ブルネイ、チリの4カ国が締結した経済連携協定が原型で、2009年11月にアメリカのオバマ大統領が5年で輸出を倍増し雇用回復を図るという方針のもとに参加の意向を表明したことから新たな自由貿易の枠組みとして注目されるに至った。
その後、オーストラリア、ペルー、ベトナム、マレーシアも参加を打ち出し、計9カ国が2011年秋のAPEC首脳会議で協定大枠合意に達した。2015年をめどに、関税の完全撤廃が目標とされている。
日本はTPPへの態度をはっきりさせていなかったが、2010年10月、当時の菅首相が突如、成長戦略の一環として「平成の開国を目ざす」と参加を表明。農業団体、地方自治体、農林関係国会議員などは「農産物の関税が撤廃されると、国内農業が壊滅する」と強く反対している。
野田首相は2011年11月、協定参加の判断を先送りしたまま「関係国との協議を開始する」との基本方針をAPEC首脳会議で表明した。これを受けてカナダ、メキシコも協議に入る意向を表明した。
TPPへの参加について、内閣府は海外への製品輸出が増えることで国内総生産を3・2兆円引き上げる効果が見込まれると試算。一方、農林水産省は安価な農産物の流入で国内農業関係分野に8・4兆円分の被害がでると試算している。
また、TPPでは公的医療保険制度の自由化・民営化も求められ、医療制度のしくみも改悪されるおそれが大きい。大企業を中心とした財界VS農家、食と医療の安心を求める消費者、民衆の利害が対立する。選挙にかけて与野党の姿勢が問われてよい重大な問題だ。
3.新たな反資本主義民衆運動の可能性に向けて
こうしたTPP問題を含めて、一体、いまどうしたらいいのか。日本の民衆のくらしはどういう形で安定させていけるのか。本当に分かりにくい時代になっている。このまま行くと八方塞がりになって選択肢が非常に少なくしか考えられない。反対ということまでは言えるが、その先がはっきりしないので閉塞感が強まる。それは日本だけではなく、世界の先進国が抱えている問題ではなかろうか。
ひとつは、外交問題としていえば、中国その他周辺アジア諸国との関係を重視して、アメリカが領導するTPPよりは、中国との関係を含めて近隣アジア諸国との協力にもっと目を向けなければならない。そのときに重要となるのは中国の体制をどう見るかという問題で、それは現代の世界像をどう理解するかという問題にも関わる。
それとともに、このような状況の下で、一体何をなすべきか。世界の左派の共通の悩みともなっている。たとえば、まもなく日本語版が出るデヴィッド・ハーヴェイの新著『資本の謎』の最終章が「なにをなすべきか」という問題を提起していて、その原稿は、世界のマルクス理論家のメール仲間で回覧され話題になっていた。ハーヴェイがそこで言っていることはいくつかあって、われわれにも大切な課題が多い。ハーヴェイによれば、社会的な諸運動がいろんな形で問題提起をしているが(例えば日本ではTPPの問題、脱原発問題、基地問題など)、それらが統合されて一つの新しい社会実現への運動に統合されていきにくいのが現代の悩みである。ソ連社会主義の崩壊以降、社会主義が理念として掲げにくくなっている。かつてわれわれに希望を与えてくれていた理念が人々の間で十分な説得力を失いつつあるのではないか。そのことが社会運動を統合して強力なものにすることを難しくしている重要な一障害である。
他方、社会変革への理念が十分に議論され、未来の希望を再生させるためには、社会運動が統合され、労働運動を基盤に市民的な諸運動を糾合してパワフルに進められないと、その基盤がみえにくい。
だから、理念と現実の社会運動の両面が、新自由主義の時代を通じて相互制約的に悪循環をなして、衰退してきている。これを好循環に転換するにはどこかから突破口を開いていかなくてはならない。ひとつでいいから、新しい希望が持てるような理念に結びつく運動が出現する、あるいはそういう方向への理念の再生が求められている。そのために何をすべきか。みんなで考えなければならない。
マルクスがバクーニンと分かれて以来、アナーキズムとマルクス主義との関係が分かれたままできている。それでいいのかということもひとつのポイントである。いま起こっているニューヨークの街頭占拠の運動などでもどこかが指令を出して組織しているのではなく、インターネットで見てグラスルーツで運動が起こり、広がっている。ある意味でアナーキーなところがある。日本でも脱原発の運動などにそういうところが感じられる。新しい人が参加してくるときに、誰かから説得されていくのではなく、自分で行きたいという自発性がある。そのような動向とこれまでの社会主義的な運動の関係性が、アナーキズムとマルキシズムの再結合を望ましいとハーヴェイに言わせるひとつの背景をなしている。
運動主体としても労働運動のほかにさまざまな地域社会その他で、NGO、NPOその他の活動が、しばしば女性に多く担われながら活性化しているところに可能性が広く存在していることにも注目しなければならない。労働運動もそれらとの連携を強化することが必要であろう。そういう提言を新社会党の中でも前向きに議論してほしい。
それとともに反資本主義の見地で、「もうひとつの世界は可能だ」と多くの国々で民衆が述べ始めていることにも十分に注目して、それらの動きが、日本でどういう形で結集されていくかということを汲みとりつつ、新社会党の力にしてほしいと願っている。
※講演録(A4判・10ページ=Wordファイルのデータ)をご希望の方は新社会党兵庫県本部までメールにてご連絡下さればお送りします。
【参考文献】
―伊藤誠『伊藤誠著作集第4巻:逆流する資本主義』『同第5巻:日本資本主義の岐路』・社会評論社・2010年。
―「日本経済のいまと今後を考ええる」『科学的社会主義』2011年2月
―「大震災・原発事故と日本経済」『科学的社会主義』2011年10月
―デイヴィッド・ハーヴェイ『資本の謎』森田成也・他訳、作品社、近刊。
いとう・まこと/1936年 東京生まれ 1959年 東京大学経済学部経済学科卒業 1961年 東京大学大学院社会科学研究科修士課程修了 1975年 東京大学経済学博士 1980年 東京大学経済学部教授 1997年 東京大学を定年退職、 東京大学名誉教授 2003年 日本学士院会員
著書は、『信用と恐慌』『資本論研究の世界』『価値と資本の理論』『資本主義経済の理論』『逆流する資本主義』『市場経済と社会主義』『日本資本主義の岐路』『日本経済を考え直す』『幻滅の資本主義』『「資本論」を読む』『サブプライムから世界恐慌へ』『伊藤誠著作集』全6巻刊行中など多数
|
 「ひょうご丹波・憲法を生かす会」と「憲法たんば」(平和憲法を守る丹波連絡会)は1月26日、篠山市民センターで京都大学原子炉実験所助教の小出裕章さんを講師に招き、「原発のウソと真実」と題する講演会を開いた(篠山市、篠山市教育委員会、神戸新聞社、丹波新聞社が後援)。会場を超満員にする380人が参加し、福島原発事故や放射能汚染の実情、その事故が問いかける人間の生き方などについて1時間半にわたって語った小出さんの講演に聴き入った。
「ひょうご丹波・憲法を生かす会」と「憲法たんば」(平和憲法を守る丹波連絡会)は1月26日、篠山市民センターで京都大学原子炉実験所助教の小出裕章さんを講師に招き、「原発のウソと真実」と題する講演会を開いた(篠山市、篠山市教育委員会、神戸新聞社、丹波新聞社が後援)。会場を超満員にする380人が参加し、福島原発事故や放射能汚染の実情、その事故が問いかける人間の生き方などについて1時間半にわたって語った小出さんの講演に聴き入った。
 小出さんは一貫して原発の危険性を訴え、各地の反原発闘争にも関わってきた研究者。福島原発事故後は、研究の傍ら休日なしで講演などのために全国を駆け回る超多忙な日々を送っており、今回の日程は昨年4月に依頼して決まったもの。そんな小出さんの講演への関心は高く、参加者は県内各地から集まった。
小出さんは一貫して原発の危険性を訴え、各地の反原発闘争にも関わってきた研究者。福島原発事故後は、研究の傍ら休日なしで講演などのために全国を駆け回る超多忙な日々を送っており、今回の日程は昨年4月に依頼して決まったもの。そんな小出さんの講演への関心は高く、参加者は県内各地から集まった。 「新社会兵庫」 2月14日号
「新社会兵庫」 2月14日号







 陸上自衛隊と米陸軍による「日米共同指揮所演習」(ヤマサクラ61)が、陸自中部方面総監部がある伊丹駐屯地を主会場に1月31日から2月5日まで行なわれた。
ヤマサクラはコンピューター・シミュレーションによる図上演習で、今回が61回目。伊丹駐屯地では00年、07年につづき3回目。陸上自衛隊約4500人、米軍約1500人のほか、オーストラリア陸軍も初のオブ参加、ソウルの在韓米陸軍も初参加して演習の指揮にあたったとされる。一時明らかになったシナリオは、中国、北朝鮮の連合軍が日本を侵略したと想定、これを撃破するというものである。
陸上自衛隊と米陸軍による「日米共同指揮所演習」(ヤマサクラ61)が、陸自中部方面総監部がある伊丹駐屯地を主会場に1月31日から2月5日まで行なわれた。
ヤマサクラはコンピューター・シミュレーションによる図上演習で、今回が61回目。伊丹駐屯地では00年、07年につづき3回目。陸上自衛隊約4500人、米軍約1500人のほか、オーストラリア陸軍も初のオブ参加、ソウルの在韓米陸軍も初参加して演習の指揮にあたったとされる。一時明らかになったシナリオは、中国、北朝鮮の連合軍が日本を侵略したと想定、これを撃破するというものである。 阪神・淡路大震災17年を前に、被災者向けに県や神戸市などがUR(都市再生機構)など民間から借り上げた復興公営住宅の返還問題についてのシンポジウムが1月14日、神戸市内で開かれた。「食い止めよう!『借り上げ公営住宅』からの追い出し」と掲げ、「被災地と被災者を考える懇談会」が主催したもので、約100人が参加した。
阪神・淡路大震災17年を前に、被災者向けに県や神戸市などがUR(都市再生機構)など民間から借り上げた復興公営住宅の返還問題についてのシンポジウムが1月14日、神戸市内で開かれた。「食い止めよう!『借り上げ公営住宅』からの追い出し」と掲げ、「被災地と被災者を考える懇談会」が主催したもので、約100人が参加した。 「憲法を生かす北区の会」と「憲法を生かす会・灘」は、脱原発運動の一環として、原発事故による福島県からの避難者の思いを聴く集いをそれぞれ持った。
「憲法を生かす北区の会」と「憲法を生かす会・灘」は、脱原発運動の一環として、原発事故による福島県からの避難者の思いを聴く集いをそれぞれ持った。 今年で第17回目となる「1・17追悼・連帯・抗議の集い」が、阪神・淡路大震災から17年の1月17日、神戸市役所前で開かれた(主催は兵庫県被災者連絡会などでつくる実行委員会)。
今年で第17回目となる「1・17追悼・連帯・抗議の集い」が、阪神・淡路大震災から17年の1月17日、神戸市役所前で開かれた(主催は兵庫県被災者連絡会などでつくる実行委員会)。 阪神・淡路大震災から17年を迎える1月17日、ひょうご労働安全衛生センターとアスベスト疾患・患者と家族の会のメンバーは神戸市三宮のフラワーロード周辺で、東日本大震災の被災地へアスベスト用マスクを届けるための募金活動を取り組んだ。
阪神・淡路大震災から17年を迎える1月17日、ひょうご労働安全衛生センターとアスベスト疾患・患者と家族の会のメンバーは神戸市三宮のフラワーロード周辺で、東日本大震災の被災地へアスベスト用マスクを届けるための募金活動を取り組んだ。 新社会党兵庫県本部の新年旗開き(「2012年新春のつどい」)が1月21日、神戸市中央区の兵庫県民会館で開かれ、党員、来賓、支援者ら約60人が参加した。党中央本部からは松枝佳宏委員長が参加し、服部良一衆議院議員(社民党)も激励に駆けつけた。
新社会党兵庫県本部の新年旗開き(「2012年新春のつどい」)が1月21日、神戸市中央区の兵庫県民会館で開かれ、党員、来賓、支援者ら約60人が参加した。党中央本部からは松枝佳宏委員長が参加し、服部良一衆議院議員(社民党)も激励に駆けつけた。