 「新社会兵庫」 5月24日号 「新社会兵庫」 5月24日号
- 明石市議選:永井5選 芦屋市議選:前田6選、山口3選
 4月17日告示、24日投開票で行なわれた統一自治体選挙・後半戦(市議選)で、新社会党兵庫県本部は明石市議選(定数31)に永井俊作(現)、芦屋市議選(定数22)に前田しんいち(現)、山口みさえ(現)の2人の計3人の公認候補を擁立するとともに、伊丹市議選(定数28)の高塚ばんこ(無所属、社民推薦・現)、宝塚市議選(定数26)の梶川みさお(社民公認・現)、大島淡紅子(社民公認・現)の2人の計3人を推薦して闘った。結果、公認の3人は当選、現有議席を維持したが、推薦候補では大島淡紅子さんだけの当選にとどまった。
公認候補が闘った2つの市議選のうち、明石市議選(投票率47・63%)では永井俊作さんが前回から約700票近く減となったが3459票を獲得して11位で5選を果たした。芦屋市議選(同前48・49%)は激戦のなか、山口みさえさんが前回票を上回る1131票を獲得、順位を5つ上げて17位で4選。前田しんいちさんは約184票減で厳しい戦いとなったが、932票の獲得で21位に入り、6選を果たすことができた。 4月17日告示、24日投開票で行なわれた統一自治体選挙・後半戦(市議選)で、新社会党兵庫県本部は明石市議選(定数31)に永井俊作(現)、芦屋市議選(定数22)に前田しんいち(現)、山口みさえ(現)の2人の計3人の公認候補を擁立するとともに、伊丹市議選(定数28)の高塚ばんこ(無所属、社民推薦・現)、宝塚市議選(定数26)の梶川みさお(社民公認・現)、大島淡紅子(社民公認・現)の2人の計3人を推薦して闘った。結果、公認の3人は当選、現有議席を維持したが、推薦候補では大島淡紅子さんだけの当選にとどまった。
公認候補が闘った2つの市議選のうち、明石市議選(投票率47・63%)では永井俊作さんが前回から約700票近く減となったが3459票を獲得して11位で5選を果たした。芦屋市議選(同前48・49%)は激戦のなか、山口みさえさんが前回票を上回る1131票を獲得、順位を5つ上げて17位で4選。前田しんいちさんは約184票減で厳しい戦いとなったが、932票の獲得で21位に入り、6選を果たすことができた。
一方、推薦候補では宝塚市議選(同前41・26%)の大島淡紅子さん(社民)は1631票で当選(21位)したが、同じく梶川みさおさん(社民)は前回から1098票減の1390票、伊丹市議選の高塚ばんこさん(無所属・社民推薦)は905票減の1140票にとどまり、共に議席を失った。
統一自治体選・後半戦も東日本大震災の影響を受けて選挙戦は盛り上がりを欠き、いずれも投票率は前回を下回った。明石市議選を除いて各市議選はそれぞれ過去最低の投票率となった。
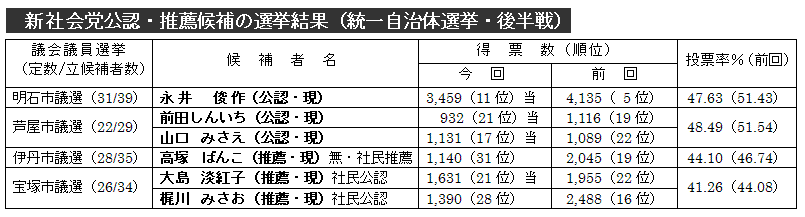
写真上:街頭で訴える永井俊作さんと運動員たち=4月16日、JR西明石駅前
写真下:(左から)永井俊作さん、山口みさえさん、前田しんいちさん、大島淡紅子さん
-
- 新社会党兵庫県本部(粟原富夫委員長)は今月29日、第16回定期大会を神戸市勤労会館で午前10時から開催する。
主な討論の課題として、①昨夏の参院選闘争、現有議席を維持した今春の統一自治体選挙闘争などの選挙闘争の総括と、それらを踏まえた自前の自治体議員づくりへのプロセスづくり、②そのための党建設の課題・目標の明確化、さらに③地域ユニオン運動の発展・強化などを担った労働運動の取り組みの総括と今後の方針、そして④憲法9条と25条を軸とする地域の大衆運動の取り組みの総括と今後の課題などが据えられている。
また、東日本大震災、福島第一原発事故をめぐる情勢を受け止め、復興支援、脱原発・エネルギー政策転換のための運動など、焦眉の運動課題にどう取り組んでいくかについても討議、方針決定される。
- 憲法25条(生存権)に焦点/「すべての人に生きる権利を」
-
「憲法64年 5・3兵庫憲法集会」が3日、神戸市中央区の兵庫県私学会館で開かれ、約300名が参加した。
 「5・3憲法集会実行委員会」(佐治孝典・実行委員長、事務局団体=自治労兵庫県本部、憲法・兵庫会議、憲法を生かす会・神戸など5団体)の主催によるもので、毎年、憲法記念日に集会を開催している。
「5・3憲法集会実行委員会」(佐治孝典・実行委員長、事務局団体=自治労兵庫県本部、憲法・兵庫会議、憲法を生かす会・神戸など5団体)の主催によるもので、毎年、憲法記念日に集会を開催している。
今年の集会のテーマは、〝生存権〟に焦点をあて「すべての人に生きる権利を―今こそ憲法25条―」。このテーマに沿って、「反貧困学習・労働教育・生存権」と題した講演を近藤美登志・大阪府高教組委員長が行なった。近藤さんは、5年前から大阪府立西成高校で取り組んでいる「反貧困学習」を紹介し、その実践にもとづいて問題を提起した。ホームレスやワーキングプアなどの社会問題、労働問題を取り上げながら、生徒たちが置かれた社会構造の問題を生徒たちと一緒に考えるなかで、「しんどい人」への共感のまなざしが育ってきていることなどを報告、「労働教育」の必要性も強調した。
集会では、連帯のエール交換として、同時刻に別の会場で憲法集会を開いていた兵庫県憲法会議から和田進・代表幹事の連帯アピールを受けた。
また、集会のテーマ〝生存権〟に因んで、①労働現場での課題、②朝鮮学校の「高校無償化」除外問題、③東日本大震災の復興支援について、全日建連帯近畿地本執行委員の倉本さん、神戸朝鮮高級学校教頭のホさん、被災地NGO恊働センターの増島さんの3人がそれぞれ報告を行なった。
集会は最後に、「東日本大震災の被災地・被災者の声が尊重され、一人ひとりの命が大切にされる復興につながるよう憲法理念を発信していこう」などと呼びかけるアピールを採択して終了した。
写真:大阪府立西成高校での「反貧困学習」の取り組みについて近藤・大阪府高教組委員長が講演した=5月3日、神戸市中央区
- 日航不当解雇争議団からも訴え
 発生から6年が経過した「JR福知山線事故」の追悼・検証集会が4月24日、国労大阪会館で開催され、国労組合員など約70人が参加した。この集会は、「JR福知山線事故」は国鉄の分割民営化がもたらしたものとして、国鉄解雇撤回闘争と結びつけながら、事故後、毎年尼崎で開催されてきた。今回は、国鉄闘争が一段落したことを受け、現場がどう変わったのか、元社長の裁判がどう推移しているのかを検証する集会として開催された。
発生から6年が経過した「JR福知山線事故」の追悼・検証集会が4月24日、国労大阪会館で開催され、国労組合員など約70人が参加した。この集会は、「JR福知山線事故」は国鉄の分割民営化がもたらしたものとして、国鉄解雇撤回闘争と結びつけながら、事故後、毎年尼崎で開催されてきた。今回は、国鉄闘争が一段落したことを受け、現場がどう変わったのか、元社長の裁判がどう推移しているのかを検証する集会として開催された。
集会のメインは、山崎元社長の刑事責任を問う神戸地裁での裁判の傍聴を続けている「JRに安全と人権を!株主市民の会」の桐生隆文さんの報告。証人のJR社員が、「事故の真相を明らかにして!」という遺族・被害者の思いを踏みにじるように、「隠す、過少評価する、嘘をつく」を繰り返していること、それが原発事故を起こした東電の体質と酷似していることを丁寧に報告した。
ついで、JR西日本の駅員と乗務員が、事故直後影をひそめていた「儲ける」が前面に出だした一例として、社員に九州新幹線開通のエンブレム(宣伝用記章)着用が強制され始めたが、安全研修で事故現場へ行くと外させるし、大震災後取り外しが指示されたことを報告した。また、新幹線の保線職場では、30年前の接触死亡事故を忘れない取り組みを続けていることが報告された。
さらに集会では、昨年大晦日にJALから指名解雇された日本航空キャビンクルーユニオンの鈴木圭子さんが、「希望退職が予定人員を上回ったのに、活動家と病弱者が解雇され、安全軽視・利益第一になっている。なんとしても勝利したい。支援を!」と訴えた。
(S)
写真:山崎・元JR西日本社長の刑事責任を問う裁判の傍聴報告も行われた=4月29日、大阪市
- 「たて・よこのコミュニケーション」テーマに
 今年で第16回を迎えた「被災地メーデー」は5月1日、雨まじりの天候のなか、昨年と同じく神戸市長田区の若松公園で開催された。
今年で第16回を迎えた「被災地メーデー」は5月1日、雨まじりの天候のなか、昨年と同じく神戸市長田区の若松公園で開催された。
今年のテーマは「たて・よこのコミュニケーション」。「無縁社会」が言われる昨今、コミュニケーションを取り戻し、壊れかけた社会をつくり直していこうという宣言だ。東日本大震災の被災地とのつながりを確認、発信していくことも重要な課題となった。実行委員会は、東北の被災地・被災者に届けるためのメッセージを花びら型のカードに書こうと呼びかけ、集めた(写真下)。
ステージでは、詩人の玉川佑香さんの詩の朗読で第1部「連帯の広場」が始まり、震災の犠牲者に黙祷を捧げた。実行委員会や来賓のあいさつののち、一方的な会社解散に伴う全員解雇と闘う関西ソフラン化工労組の組合員たちが子どもも含めた家族とともに、その闘争を寸劇にして演じ、支援を呼びかけた。東日本大震災の復旧支援にボランティアに行った仲間からの報告も行なわれた。
 第2部「熱唱&熱笑in新長田」では、おなじみの南米音楽のグルーポ・マルテス新長田や岡本光彰さん、「はるまきちまき」さんらの歌や旭堂南陵さんの講談などが登場。今年の新顔、女性4人組のGreen2(グリーングリーン)の見事な歌声が称賛を浴びた。
第2部「熱唱&熱笑in新長田」では、おなじみの南米音楽のグルーポ・マルテス新長田や岡本光彰さん、「はるまきちまき」さんらの歌や旭堂南陵さんの講談などが登場。今年の新顔、女性4人組のGreen2(グリーングリーン)の見事な歌声が称賛を浴びた。
写真:祭典の第1部では解雇反対闘争を題材にした寸劇も登場した=5月1日、神戸市長田区
- 市民グループが集会とパレード
 福島第一原発の事故を受け、原発の危険性を訴えるとともに、原発に頼らない社会を考え、つくっていこうと、食や農の問題に取り組む市民グループなど15団体が呼びかけた集会が4月29日、神戸市中央区の東遊園地で開かれた。
福島第一原発の事故を受け、原発の危険性を訴えるとともに、原発に頼らない社会を考え、つくっていこうと、食や農の問題に取り組む市民グループなど15団体が呼びかけた集会が4月29日、神戸市中央区の東遊園地で開かれた。
「さよなら原発 神戸アクション」と名づけられたこの日の行動には子どもたちも含めて約300人が集まり、反原発・脱原発の運動に取り組む人たちが、歌や紙芝居なども交えて各地の原発をめぐる状況や運動の報告・意見をリレートークで述べ合った。今回、福島県で東日本大震災に被災し、大阪に移住してきた人も発言した。また、集会では、若狭湾に14基の原発がある現実を踏まえ、関西電力に対し、すべての原発を停止することや福島第一原発の事故についての話し合いを求める要望書を5月16日に提出することが提案され、了承された。
集会後は、アフリカンドラムやギターなどで音楽を流しながら、龍のデコレーションや色とりどりの横断幕、プラカードなどを掲げて繁華街をパレード、通行人や買い物客に反原発・脱原発を訴えた。
写真:市民約300人が集まって脱原発をアピールしたパレード=4月29日、神戸市中央区
- 東日本大震災 福島県相馬市で支援活動
ろっこう医療生活協同組合 大倉 均
避難所の統合、移動でストレス
東日本大震災発生から約1カ月後の4月8日から11日間、ろっこう医生協の第2次支援活動の一員として福島市、相馬市に入りました。
福島市内の避難所は、高校の体育館や公立の学習センターなどが使用され、避難者は主に原発の周辺地域、浪江町や南相馬市などの方たちでした。1カ月も経つと、小さな避難所や学校は縮小・解消され、「総合運動公園」などの大きな公立の体育館的な施設に統合、移動させられつつありました。市内の県立高校避難所では、避難者たちは移動するたびに新たに始まる人間関係でストレスが溜まり、心底疲れて毛布の上でぐったりされているようでした。とくに病院にかかっている高齢者や保育施設の必要な幼児、小学生などを抱えている家族は、避難所を簡単には替えることができず意見の相違も生じ、家族関係にも影響しているようでした。
相馬市の避難所でボランティア活動
私は4月11日から相馬市に移動し、海岸から3、4キロ離れた市役所近くの旧相馬女子高校の避難所に入りました。避難者は約500人、ほぼ全員が原発避難の南相馬市からでした。
 避難者は高齢者が6、7割で、生物教室など約40教室に布団や毛布を敷詰め、プライバシーが保たれない所で過ごし、また、1階にあるトイレまで行くのに3階、2階からは階段を使わざるを得ず、とても大変そうでした。ある日、夜11時過ぎ、90歳近いおばあさんが1階の廊下をトイレに向かってゆっくり歩いていると、30歳くらいの孫が杖を持って慌てて走って来ました。理由を聞くと、おばあさんはトイレに行くのに迷惑をかけまいと、夜になって静かに教室を抜け出てきたというのです。孫はそんなおばあさんに気づいて追いかけてきたとのことでした。食事もおにぎりやパンが続き、またトイレも控えようとして水分を取らず、そのようなお年寄りが体調を崩しているようでした。受付けに座っていると、簡易おむつ等を取りにくる避難者が多かったのはそんな理由からだったのでしょうか。
避難者は高齢者が6、7割で、生物教室など約40教室に布団や毛布を敷詰め、プライバシーが保たれない所で過ごし、また、1階にあるトイレまで行くのに3階、2階からは階段を使わざるを得ず、とても大変そうでした。ある日、夜11時過ぎ、90歳近いおばあさんが1階の廊下をトイレに向かってゆっくり歩いていると、30歳くらいの孫が杖を持って慌てて走って来ました。理由を聞くと、おばあさんはトイレに行くのに迷惑をかけまいと、夜になって静かに教室を抜け出てきたというのです。孫はそんなおばあさんに気づいて追いかけてきたとのことでした。食事もおにぎりやパンが続き、またトイレも控えようとして水分を取らず、そのようなお年寄りが体調を崩しているようでした。受付けに座っていると、簡易おむつ等を取りにくる避難者が多かったのはそんな理由からだったのでしょうか。
避難者の諸問題、義援金、入退所、郵便物取り扱い、運転免許証再交付、医療団・炊き出し隊・来所ボランティア・救援物資の受入れ等、その対応は南相馬市職員が中心を担い、総括責任者1名、副責任者1名の隔日交代、一般職員は4班(班員3名)の3交代、看護班3名、女性班2名のローテーションで、実家を流失したり、親戚の方を亡くしている職員も参加していました。
電話対応や避難者への日用品の受け渡しなどの対応は相馬市職員が2名、毎日交代でした。両親は首まで水につかりながらも助かったが実家を流失したという職員もいました。また、自治労埼玉からも1名が1週間交代で受付業務をサポート、福島市からは若い県職員が4名ずつ、2泊3日で交代しながら炊事当番を中心に参加していました。
避難所の運営担当者ミーティングは毎朝8時から開かれ、引継ぎ事項や当日の主な流れを確認しました。リーダー会議(各部屋の代表で構成。当初、約50名)は毎夜7時から、南相馬市の責任者を進行役として、避難生活上の1日の振り返りやルール作り、明日の予定、市や県からの情報伝達などを行ないました。
12日、宮崎県から大型トラックが到着し、それまでのパン・おにぎり中心のメニューから、野菜、海産物入りの温かい汁物が登場。1週間でしたが皆さんに笑顔が戻りました。その後も、ワカメの酢の物(寺院)、魚と大根のアラ汁(病院)、アジの開き(地元の業者)、ちゃんこ鍋(相撲部屋)などが届きました。
各教室では毛布に横たわる避難者が多く、運動不足が続き、不健康な生活のようでした。大分県のボランティアチームが朝10時と昼3時の2回、放送で窓を開けて換気するよう促し、「ラジオ体操1番」のテープをかけると、避難者の何人かが廊下で体操をしていました。私もマイクを握り、放送を通じて事前に数分間、肩周りストレッチを呼びかけ、俄かインストラクターを務めました。
 被災者の方の表情は険しく、笑い声もほとんど無く、楽しく会話している姿はあまり見られませんでした。声を掛けると、畑のこと、息子の遺体がやっと見つかってホッとしたこと、仕事がやっと再開すること、体重が3キロ減ったこと、飼っていた牛や犬がどうなっているだろうかなど、いろいろな話が返ってきました。我が家・土地への思いは想像以上だと思いました。
被災者の方の表情は険しく、笑い声もほとんど無く、楽しく会話している姿はあまり見られませんでした。声を掛けると、畑のこと、息子の遺体がやっと見つかってホッとしたこと、仕事がやっと再開すること、体重が3キロ減ったこと、飼っていた牛や犬がどうなっているだろうかなど、いろいろな話が返ってきました。我が家・土地への思いは想像以上だと思いました。
子どもたちは空き教室で、被災地の先生や塾の教師、保護者たちによって、午前中は小中学生(約30人)、午後は高校生(約20人)の臨時の学習教室が開設されていました。
赤ちゃんから6歳くらいまでの幼児のための保育所的なものはありませんでした。若い親たちは赤ちゃん連れでは役所にも、仕事探しにも行くのは難しく、赤ちゃんを預かる場所や見てくれる人を何とかしたいと市の職員は悩んでいました。
避難所を訪ねたボランティアは、散髪、炊き出し、医療、針灸マッサージ、お風呂作り、情報ツールで情報収集のアイデア提供、傾聴活動などいろいろでした。
息の長い支援活動を
今回の震災は、阪神・淡路大震災以上に深刻な状況です。被災者は今後も長期にわたって苦悩・苦難の日々が続きます。
私たちは16年前に被災し、支え合ったあの頃を忘れず、今こそ皆で「無縁社会」から「築縁」への機会にしようではないかと思いました。16年前、神戸の街を走る他県の消防車や法被姿の消防団、避難所に乗りつけた歯科の移動マイクロバスに涙し、勇気をもらったと私は強く思っています。私たちはそれぞれの立場でできることは何か、被災者の気持ちに近づく努力をしながら、みんなで知恵を出し合い、できそうな事を考え、息の長い支援活動をしていきたいと思います。
と同時に、私たちが決して忘れてはならないのは、今回のような避難者をつくったのは、原発事故という人災だということです。そして、これ以上の大惨事を起こさないために、私たちはすべての原発を閉鎖する運動を進めるべきだと思います。
写真上:避難所での朝のミーティング=相馬市
写真下:プライバシーの守れない教室での避難所生活が続いた=相馬市
|
 4月17日告示、24日投開票で行なわれた統一自治体選挙・後半戦(市議選)で、新社会党兵庫県本部は明石市議選(定数31)に永井俊作(現)、芦屋市議選(定数22)に前田しんいち(現)、山口みさえ(現)の2人の計3人の公認候補を擁立するとともに、伊丹市議選(定数28)の高塚ばんこ(無所属、社民推薦・現)、宝塚市議選(定数26)の梶川みさお(社民公認・現)、大島淡紅子(社民公認・現)の2人の計3人を推薦して闘った。結果、公認の3人は当選、現有議席を維持したが、推薦候補では大島淡紅子さんだけの当選にとどまった。
公認候補が闘った2つの市議選のうち、明石市議選(投票率47・63%)では永井俊作さんが前回から約700票近く減となったが3459票を獲得して11位で5選を果たした。芦屋市議選(同前48・49%)は激戦のなか、山口みさえさんが前回票を上回る1131票を獲得、順位を5つ上げて17位で4選。前田しんいちさんは約184票減で厳しい戦いとなったが、932票の獲得で21位に入り、6選を果たすことができた。
4月17日告示、24日投開票で行なわれた統一自治体選挙・後半戦(市議選)で、新社会党兵庫県本部は明石市議選(定数31)に永井俊作(現)、芦屋市議選(定数22)に前田しんいち(現)、山口みさえ(現)の2人の計3人の公認候補を擁立するとともに、伊丹市議選(定数28)の高塚ばんこ(無所属、社民推薦・現)、宝塚市議選(定数26)の梶川みさお(社民公認・現)、大島淡紅子(社民公認・現)の2人の計3人を推薦して闘った。結果、公認の3人は当選、現有議席を維持したが、推薦候補では大島淡紅子さんだけの当選にとどまった。
公認候補が闘った2つの市議選のうち、明石市議選(投票率47・63%)では永井俊作さんが前回から約700票近く減となったが3459票を獲得して11位で5選を果たした。芦屋市議選(同前48・49%)は激戦のなか、山口みさえさんが前回票を上回る1131票を獲得、順位を5つ上げて17位で4選。前田しんいちさんは約184票減で厳しい戦いとなったが、932票の獲得で21位に入り、6選を果たすことができた。



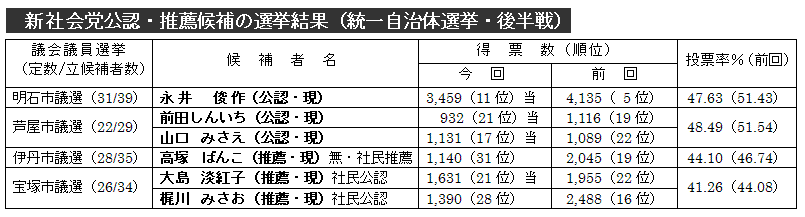 写真上:街頭で訴える永井俊作さんと運動員たち=4月16日、JR西明石駅前
写真上:街頭で訴える永井俊作さんと運動員たち=4月16日、JR西明石駅前 「新社会兵庫」 5月24日号
「新社会兵庫」 5月24日号







 「5・3憲法集会実行委員会」(佐治孝典・実行委員長、事務局団体=自治労兵庫県本部、憲法・兵庫会議、憲法を生かす会・神戸など5団体)の主催によるもので、毎年、憲法記念日に集会を開催している。
「5・3憲法集会実行委員会」(佐治孝典・実行委員長、事務局団体=自治労兵庫県本部、憲法・兵庫会議、憲法を生かす会・神戸など5団体)の主催によるもので、毎年、憲法記念日に集会を開催している。 発生から6年が経過した「JR福知山線事故」の追悼・検証集会が4月24日、国労大阪会館で開催され、国労組合員など約70人が参加した。この集会は、「JR福知山線事故」は国鉄の分割民営化がもたらしたものとして、国鉄解雇撤回闘争と結びつけながら、事故後、毎年尼崎で開催されてきた。今回は、国鉄闘争が一段落したことを受け、現場がどう変わったのか、元社長の裁判がどう推移しているのかを検証する集会として開催された。
発生から6年が経過した「JR福知山線事故」の追悼・検証集会が4月24日、国労大阪会館で開催され、国労組合員など約70人が参加した。この集会は、「JR福知山線事故」は国鉄の分割民営化がもたらしたものとして、国鉄解雇撤回闘争と結びつけながら、事故後、毎年尼崎で開催されてきた。今回は、国鉄闘争が一段落したことを受け、現場がどう変わったのか、元社長の裁判がどう推移しているのかを検証する集会として開催された。 今年で第16回を迎えた「被災地メーデー」は5月1日、雨まじりの天候のなか、昨年と同じく神戸市長田区の若松公園で開催された。
今年で第16回を迎えた「被災地メーデー」は5月1日、雨まじりの天候のなか、昨年と同じく神戸市長田区の若松公園で開催された。 第2部「熱唱&熱笑in新長田」では、おなじみの南米音楽のグルーポ・マルテス新長田や岡本光彰さん、「はるまきちまき」さんらの歌や旭堂南陵さんの講談などが登場。今年の新顔、女性4人組のGreen2(グリーングリーン)の見事な歌声が称賛を浴びた。
第2部「熱唱&熱笑in新長田」では、おなじみの南米音楽のグルーポ・マルテス新長田や岡本光彰さん、「はるまきちまき」さんらの歌や旭堂南陵さんの講談などが登場。今年の新顔、女性4人組のGreen2(グリーングリーン)の見事な歌声が称賛を浴びた。
 福島第一原発の事故を受け、原発の危険性を訴えるとともに、原発に頼らない社会を考え、つくっていこうと、食や農の問題に取り組む市民グループなど15団体が呼びかけた集会が4月29日、神戸市中央区の東遊園地で開かれた。
福島第一原発の事故を受け、原発の危険性を訴えるとともに、原発に頼らない社会を考え、つくっていこうと、食や農の問題に取り組む市民グループなど15団体が呼びかけた集会が4月29日、神戸市中央区の東遊園地で開かれた。 避難者は高齢者が6、7割で、生物教室など約40教室に布団や毛布を敷詰め、プライバシーが保たれない所で過ごし、また、1階にあるトイレまで行くのに3階、2階からは階段を使わざるを得ず、とても大変そうでした。ある日、夜11時過ぎ、90歳近いおばあさんが1階の廊下をトイレに向かってゆっくり歩いていると、30歳くらいの孫が杖を持って慌てて走って来ました。理由を聞くと、おばあさんはトイレに行くのに迷惑をかけまいと、夜になって静かに教室を抜け出てきたというのです。孫はそんなおばあさんに気づいて追いかけてきたとのことでした。食事もおにぎりやパンが続き、またトイレも控えようとして水分を取らず、そのようなお年寄りが体調を崩しているようでした。受付けに座っていると、簡易おむつ等を取りにくる避難者が多かったのはそんな理由からだったのでしょうか。
避難者は高齢者が6、7割で、生物教室など約40教室に布団や毛布を敷詰め、プライバシーが保たれない所で過ごし、また、1階にあるトイレまで行くのに3階、2階からは階段を使わざるを得ず、とても大変そうでした。ある日、夜11時過ぎ、90歳近いおばあさんが1階の廊下をトイレに向かってゆっくり歩いていると、30歳くらいの孫が杖を持って慌てて走って来ました。理由を聞くと、おばあさんはトイレに行くのに迷惑をかけまいと、夜になって静かに教室を抜け出てきたというのです。孫はそんなおばあさんに気づいて追いかけてきたとのことでした。食事もおにぎりやパンが続き、またトイレも控えようとして水分を取らず、そのようなお年寄りが体調を崩しているようでした。受付けに座っていると、簡易おむつ等を取りにくる避難者が多かったのはそんな理由からだったのでしょうか。 被災者の方の表情は険しく、笑い声もほとんど無く、楽しく会話している姿はあまり見られませんでした。声を掛けると、畑のこと、息子の遺体がやっと見つかってホッとしたこと、仕事がやっと再開すること、体重が3キロ減ったこと、飼っていた牛や犬がどうなっているだろうかなど、いろいろな話が返ってきました。我が家・土地への思いは想像以上だと思いました。
被災者の方の表情は険しく、笑い声もほとんど無く、楽しく会話している姿はあまり見られませんでした。声を掛けると、畑のこと、息子の遺体がやっと見つかってホッとしたこと、仕事がやっと再開すること、体重が3キロ減ったこと、飼っていた牛や犬がどうなっているだろうかなど、いろいろな話が返ってきました。我が家・土地への思いは想像以上だと思いました。