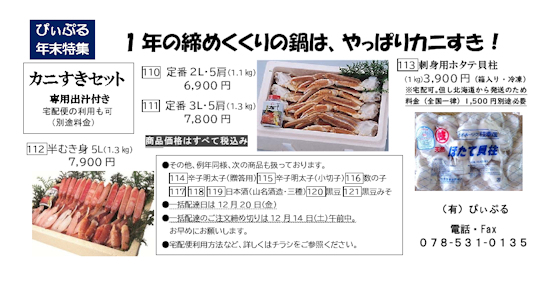「新社会兵庫」 12月10日号 「新社会兵庫」 12月10日号
- 「戦後政治の総決算」「臨調行革」「3公社民営化」「日本列島不沈空母化」……、その人物を表すキーワードは実に多い。中曽根康弘元首相が先日、死去した。死を伝える記事ではこれらの言葉が並べられ、大抵のメディアが彼を「大きな政治家」として描き讃えた▼だが、立場を違えれば、彼こそが日本をとんでもない方向に導いていった張本人ではないか。国鉄の民営・分割化等の断行、日米同盟の強化、原発政策の推進……。当時、米国のレーガンや英国のサッチャーとともに「小さな政府」を標榜し、グローバルな新自由主義政策を展開した。格差と貧困が広がり、社会が引き裂かれている今日の世情の礎石を築いた人物である。そのために総評、社会党を解体し、労働者階級に多大な犠牲を強いた人物である▼彼の死去で、日本の新自由主義の来し方をあらためて振り返る機会を得た。彼がぶち上げた、日本社会の構造を変えていく政策は、ほとんどがその通りに推進されていったことを見るとおぞましい▼ただ、「行革でお座敷をきれいにして床の間に新憲法を安置する」という改憲宣言はどうだ。たしかにお座敷は相当にきれいにされてしまったが、まだ新しい憲法はそこには据えられていない。

- 「ロスジェネ」世代に注目を
-
参院選とロスジェネ
今年の参院選の特徴の一つが、政治の舞台にロスジェネが登場したことである。ロスジェネは、これまで政治や社会問題に距離を置いている感が強かった。だが、参院選においてロスジェネを表明し、非正規や様々な不合理に直面してきた体験をもとに、政治や社会を変えたいという候補者が出現した。社民党比例区候補者の大椿ゆう子さんがもっとも典型的だったが、立憲民主党や共産党からもロスジェネを表明した候補者が現れた。
さらに、「れいわ新選組」は明らかにロスジェネにターゲットをあてた選挙戦をおこない、ロスジェネの心をつかみ、票と議席に結びつけることに成功した。
ロスジェネが、政治と社会に目を向け始めたのだ。
ロスジェネとは
ロスジェネは「ロスト・ジェネレーション=失われた世代」の略語である。バブル経済がはじけて長期にわたって低迷し、大学を卒業した時に就職難や非正規労働につかざるをえなかった1970〜1982年生まれの世代だ。今では36〜49歳になっている。最近では「就職氷河期世代」とも言われ始めている。
ロスジェネと日本社会
ロスジェネが子どもだった時代(70年代後半から80年代)は、いま振り返ってみると、そこそこ豊かでゆとりのある社会だった。しかし底流では、臨調行革による職場の締め付けや「権理」(注)破壊が進行していた。総評や社会党が無力化し、解体に追い込まれる時代であった。ついにはバブルに踊らされ、気がつくと荒涼たる社会になっていたのである。
ロスジェネが社会人として体験したのは、バブルではなく就職難であり、多くが非正規労働に追い込まれた。彼らのほとんどは、親世代と違った社会生活に入らざるをえなかった。しかし、なかには少数の成功者がおり、落ちこぼれたものは自他共に「自己責任」で納得せざるをえなかった。「周りや社会には頼れない、自分で何とかするしかない」と心底思い知らされた世代である。
ロスジェネと親世代
ロスジェネの親は、ほとんどが団塊世代である。団塊世代は学生運動や労働運動に積極的に参加した。とくに活動家の子どもたちは、保育園や小学校低学年のときには、土日・夜の集会や学習会に連れて行かれた。彼ら、彼女らにはその内容は理解できなかっただろうが、親の瞳の輝きのなかに明るい未来を見ていたかもしれない。
だが90年代に入ると暗い時代が続いた。国労攻撃は熾烈を極め、職場は「競争と服従」の場になった。社会党は方向を見失い、民主党、社民党、新社会党に3分裂した。
そのなかで新社会党は、「矛盾の激化は新自由主義に基づくものであり、闘うことでしか展望はつかめない」という路線を貫いた。だが結果として、党勢を伸ばすことはできず、政党要件も失った。それでも、新社会党員は闘い続けた。ロスジェネからは「もっと上手にやってよ」と思われ続けた歳月であった。
ロスジェネに変化が
だが最近になって、変化が見えてきたように思う。「このままでは大変なことになる。自分なりに社会をなんとかしなければ」というロスジェネが周囲に出現し始めている。
そういう位置に立ってみて、「新社会党って、結構きちんとやってるやん」「成果をあげてはいないけど、親たちは頑張ってきたんや」という認識が生まれているようだ。
とりわけ、新社会党兵庫県本部には大きな変化が起きている。郵便局の組合活動や、尼崎の統一地方選挙などで、入党の流れができ始めている。『新社会兵庫』でもロスジェネ発の記事が相次いでいる。最近では、SNSを活用した「新社会党サポーターズ(仮称)」も検討されている。
身近なロスジェネと対話を
この変化に注目して、ロスジェネとの対話を提起したい。子ども、孫、甥や姪など身近にいる彼ら彼女らに、安倍政権のひどさや社会の矛盾について、改めて問いかけてほしい。今や『闘わなければ社会が壊れる』(今野晴貴・藤田孝典編、岩波書店)時代であることが確認できるのではなかろうか。
すぐに、活動を始めるのは無理であれば、『週刊新社会』や『新社会兵庫』を購読することからはどうだろうか。ぜひ、ご検討をお願いしたい。
※(注)「権利」でなく「権理」とした。なぜかについては、別の機会に述べたい。
佐野修吉(新社会党須磨総支部副委員長)

- 組織を維持することの大変さ
- 今年の1月17日に加古郡稲美町にあるF興業という少人数の運送会社の7人が、賃金・労働条件のことで社長に改善を求めてきたが受け入れてくれない、とユニオンに相談に来られた。
7人はユニオンに加盟して、F興業の組合分会を結成したことを会社に通告。賃金・労働条件の改善の要求書を提出して団体交渉の開催を申し入れた。会社は、組合が組織されたことで申し入れを無視できず、団体交渉には応じてきた。
しかし、団体交渉の場では、会社は要求された事柄には口頭のみの回答を通したため、分会は書面による回答を求め、押し問答となった。抗議の結果、文書で提示すると回答したが、のちの団体交渉での提示を求めたところ、日程の引き延ばしをしてきた。再三にわたって申し入れを行った結果、5月末までに「就業規則・賃金規程」を提示して説明したいと回答してきた。
提示された内容を全組合員で検証し、修正および挿入が必要な点を要求にまとめ、団体交渉を行った。会社が組合の要求に理解を示したので、けっして十分ではなかったが一定のけじめをつけることとした。
就業規則・賃金規程が整理されたことを受け、今後の取り組みをどうしていくか、組合員の間で議論した。確認された方針は、会社に対して個別の要求を行い、交渉をするということだった。まずはじめに夏季一時金の要求をしようとなった。現状は社長の「胸三寸」で寸志として支給されていた。組合員ひとりひとりの意思表示として、要求額は全組合員で決め、団体交渉をすることを確認した。
要求書を提出する寸前になって、分会長からユニオン委員長に突然、「ユニオンを脱退したい」と連絡をしてきた。理由は、「就業規則・賃金規程ができたので今後は独自で取り組んでいく」とのことだった。ユニオンは今後、分会が独り立ちの運動ができるように手助けする方針を決めた矢先だった。
これまでも相談を受け、問題が解決するとユニオンを脱退していくという苦い経験を何度もしてきたが、まったく労働組合と縁のない労働者をどう組織し、維持していくか、たいへんな課題であることをあらためて実感させられた。
岩本義久(はりまユニオン書記長)

- いま教育の現場では
-
 戦争体験を語れなかった父たちの世代の気持ちが少し分かる気もする。自分の醜さはふり返りたくない。
戦争体験を語れなかった父たちの世代の気持ちが少し分かる気もする。自分の醜さはふり返りたくない。
体罰、ハラスメント、教育をめぐる「不祥事」が続出し、40余年教員を続けてきた私自身、どこに出口が見いだせるのか、悶々としている。
退職し、学校世界から離れた今でこそ、こうあるべきと指摘し、批判もできるけれど、現役時代の自分はどうだったのか。「不祥事」を生み出すドロドロのなかにいてどこまで抗ってきたのか。学級がうまくいかず(それはとりもなおさず子どもを苦しめ、成長の機会を奪ったということ)、休職したこともあった。以降、それを負い目に働き続けた日々があった。保護者による担任アンケート、学力テスト……、じわじわと追われてきて気が付けば休み時間に職員室に戻ってきてもだれもいない風景が当たり前になっていた。子どもより早く教室に行って「おはよう!」と迎える、朝に一仕事もあたりまえ。もちろん、勤務時間開始前に。
今、縁あって現役の先生たちの組合のお手伝いをしている。やっと引き受けてくれた役員もなかなか会議に集まれず、月2回だった会議を1回に減らして、それでもそろわない会議の中で動員などの日程調整ぐらいで終わってしまう。
低い組織率の中で役員を引き受けてくれたこの面々でさえ、飲み会では「組合がなんであるのかわからへん」「給料が上がるのは非組も一緒」「正直、なくても困れへん」。
子どもの見方にしても、日々格闘し、良かれと思って追い立てているからこそ、努力できない子、結果を出せない子を「結局、自己責任や」と見てしまっている。この子らの背景にある生活が社会の問題として見えないまま。
新聞も読んでいるのだろうか。「前川喜平の講演会」といっても「名前は聞いたことあります」という現状。
教師としてやるべきことがマニュアル化され、教師の「スタンダード」が年々更新されて、教育内容も、行事も、研究も「ビルド」はあっても「スクラップ」はまずない。
「しんどい」「目一杯!」という声も聞くけど、ケロッとさわやかな顔で仕事をこなしている風でないと居られないんじゃないだろうか。若い人に言われたことがある。「私たち、怒りをぶつけている姿には引いてしまいます」。
昨年、新任の組合員が1学期が終わったところで休職し、年度末を待たず辞めていった。学年で過重な仕事を押し付けられるハラスメントがあったという。ずっと連絡を取り、話を聞いてきた組合役員も最後は「『辞めたらあかん』と言うてたら、よけい彼を追い込むのと違いますか」と転職を考える彼に共感していった。
「子どもの人権を守る」「主権者として育てる」―そのために、人として尊重されるとはどういうことなのか、まず教員自身が我がこととして実態をもっと分かり、追求しようとしていなければ始まらない。そんな「ほんとの声」をあげられる場所を少しでも作っていきたい。
(M)
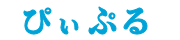
|
 「新社会兵庫」 12月10日号
「新社会兵庫」 12月10日号



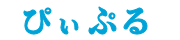








 戦争体験を語れなかった父たちの世代の気持ちが少し分かる気もする。自分の醜さはふり返りたくない。
戦争体験を語れなかった父たちの世代の気持ちが少し分かる気もする。自分の醜さはふり返りたくない。