 「新社会兵庫」 12月11日号 「新社会兵庫」 12月11日号
- 安倍一強と言われるが、本当にそうなのか。楽屋と舞台を仕切っていた政財の幕が、最近はますます透けて見えるようになり、「喫緊」「喫緊」と言わされている腹話術人形のようだ▼「働き方」国会の時もそうだが、法の中身は後で考えますとか、前提の統計に誤りがありました、とかいうパターンが増えている。質問に答えられず、ただその項目を繰り返す馬鹿々々しさもひどくなっている。「なぜ青なのか?その色を青と言うからです」という調子だ▼もともと審議されるのがいや(そもそも審議に堪えるしろものではないが)な政権には、形式さえ整えば、それで充分なのだ▼審議不十分だ、中身がスカスカだと突っ込まれて、それでは後でやりましょう、というのでは立法府に値しないだろう。民主主義の仮面さえつけられないだろう▼首相の外交日程のために、国権の最高機関が穴だらけになっていいのだろうか。それが許されるとならば、悪知恵の働く自民党の古狸ども、わざと首相日程を窮屈につくり、その間にさらに窮屈に国会日程を設定し、十分な審議はできない、審議省略など言い出すだろう▼産業界の「喫緊」は、国会の日程を曲げたり、切り刻んだりしてもいい理由にはならない。

- 働く者の痛み・怒りに寄り添い 地域ユニオンの拡大へ
- ひょうごユニオンは1998年3月28日、「働く誰もが安心して相談できる拠点を広げよう」をスローガンに掲げて誕生した。今年で結成20周年を迎えたことになる。
その契機となったのが1995年の阪神・淡路大震災である。このとき、大震災を理由に5万人とも10万人ともいわれる「震災解雇」が発生した。この首切り問題を正面から取り上げたのが神戸ワーカーズユニオンと武庫川ユニオンだった。全国のユニオンの支援を得て開設した「阪神大震災 労働・雇用ホットライン」の相談数は半年で1700件に達した。交渉企業は50社以上、対象労働者は約1万人におよんだ。
そして翌96年11月、神戸市北区のしあわせの村で開催されたコミュニティ・ユニオン全国交流集会は、兵庫のユニオン運動を広げる跳躍台となった。その後、芦屋(97年12月)、姫路(98年5月)、明石(99年2月)でも地域ユニオンが結成され、そうした流れのなかで県内の地域ユニオンの連合体としてひょうごユニオンが誕生した。
あれから20年、働く者をとりまく環境は一変した。非正規雇用は労働者の約4割を占め、賃金は1997年をピークに下がり続けている。かつて「1億総中流」「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と世界の人々がうらやんだ日本は、今とても“生きづらい社会“となっている。私たちの回りには、格差、貧困、ワーキングプア、ブラック企業、いじめ・パワハラ、過労自殺、自己責任などの言葉が溢れている。
そして何より残念なのは、働く者の最大のセーフティーネットとなるべき労働組合の姿が見えないことだ。日本の労働組合組織率は17・1%、企業規模100人未満はわずか0・9%である。組織率に限って言えば、アメリカ10・7%、イギリス23・2%、ドイツ17%、韓国は10・2%だ。各国とも労働者の同質性が崩れ、後退を余儀なくされている。しかし、日本の労働組合ほど労働者から信頼を失い、社会的影響力を低下させた国はないだろう。欧米や韓国では労働組合の旗がひるがえっており、ストライキが皆無の日本とは雲泥の差がある。
先の国会では「働き方改革」という美名のもとに、定額働かせ放題・過労死促進法と言われる「高度プロフェショナル制度」の導入が強行された。世界の労働者が命がけで確立した「1日8時間労働制」の根幹を突き崩す悪法である。これに対し、日本労働弁護団や野党、全国過労死を考える家族の会、コミュニティ・ユニオン等は、労働法制改悪阻止に向けて全国キャラバンや抗議集会を展開した。けれども、連合を中心とする既存の労働組合の反応は総じて鈍かったと言わねばならない。
日本の労働組合は「企業主義」であり、欧米のような権利闘争の歴史もなく、韓国のように独裁政権を倒した成功体験を持たない。だからと言って、低迷する労働組合の現状を「しかたがない」と諦めるならば、それこそ労働運動に展望はないだろう。私は労働組合が弱体化した最大の要因は、労働組合の活動をもっぱら賃上げ闘争に特化し、人間としての尊厳や労働者の権利を守るたたかいを真剣に取り組んでこなかったことにあると思っている。
したがって、私たちはこれを反面教師に、働く者の痛み、怒りに寄り添い、たとえ小さくともキラリと光るたたかいを通して、地域ユニオンを拡大していくことが求められている。労働組合が再び元気を取り戻すためには、既存の企業別労働組合と1人でも誰でも入れる地域ユニオンの連携強化は不可欠である。なぜなら、「最も組合を必要とする」人びとの圧倒的多数は未組織である。その労働者を置き去りにして労働運動が前進することはない。
その立場から、私たちは来年10月にコミュニティ・ユニオン全国交流集会を兵庫・姫路で開催する。その成功に向けて2月16日、加古川勤労会館でスタート集会を予定している。19春闘や統一地方選挙の最中ではあるが、多くの働く仲間に参加してもらいたい。
安倍政権を退陣に追い込み、改憲の野望を打ち砕くためには、労働運動の再生・強化は避けて通れない課題である。
岡崎 進(ひょうごユニオン委員長)

- 兵高連が恒例の秋期合宿で交流
- 熟年者ユニオンも参加する兵庫県高齢者団体連絡会(兵高連)の第4回秋季合宿が11月9日~10日、宍粟市波賀町のフォレストステーション波賀で開かれた。今回はこの秋季合宿の報告を熟年者ユニオンからの報告としたい。
講師に熟年者ユニオンの会員でもある永井俊作明石市議を迎えての合宿だった。
講演のテーマは「安倍政権の問題点」で、①70歳年金支給の問題、②来年度予算の問題点、③「働き方改革」法をめぐる問題、④子育て・介護(保険)問題、⑤自衛隊・米軍の一体化と沖縄問題と、幅広く多岐にわたった講演内容であった。
介護問題では、介護保険制度の改悪として、明石市職員数の推移を具体的に示しながら、介護を受ける高齢者も介護職員もますますサービスや労働条件が悪くなっていくことが明らかにされた。
こうした福祉切り捨ての一方で、「法人税減税」と「軍事費増大」があり、「日米地位協定」が全く守られていない現実があることが述べられた。辺野古新基地建設問題では、沖縄県は埋立地が軟弱地盤であることを示して埋立承認撤回理由書を沖縄防衛局に提出している。V字滑走路の先端は水深30mの海底の土壌(厚さ40m)がマヨネーズのような超軟弱地盤で、N値ゼロ(基礎の捨て石や大型ケーソンが土壌の下まで沈んでしまう)と確認されているという。さらに、具体的な犯罪数をあげながら海兵隊の質が低下しているとの指摘もあった。
質疑応答もあった最後には、次世代にいかに今日のような話を理解してもらうようにしていくかが課題だ、の話になった。
今回の合宿の開催地としてフォレストステーション波賀のコテージの1棟(10名用)を借りたが、民宿などの利用と比べて安く利用できた。10名用のコテージには風呂もあり、10名が論議できる部屋と寝室(1F、2F)があって夜遅くまで交流ができた。翌日は、原不動滝と紅葉を楽しんで2日間の日程を終えた。
横林賢二(熟年者ユニオン事務局次長、兵高連事務局長)

- 描き続けて13年
-
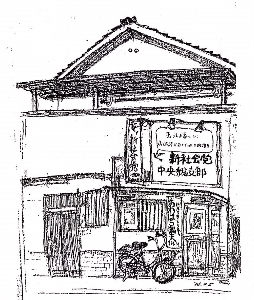 中央総支部では、支持者の方々とつながるため『新社会中央区版』を毎月発行していますが、その一角に「純子のスケッチブック」というコーナーをいただいています。2006年5月の97号から最新の11月・180号まで続いています。上手ではありませんが、絵を描くのは好きなので、私にとってはとてもうれしいものです。
中央総支部では、支持者の方々とつながるため『新社会中央区版』を毎月発行していますが、その一角に「純子のスケッチブック」というコーナーをいただいています。2006年5月の97号から最新の11月・180号まで続いています。上手ではありませんが、絵を描くのは好きなので、私にとってはとてもうれしいものです。
こだわりとして、新年号には近辺の神社・仏閣を、その他はできるだけ中央区の建物、風景を描いてきました。時々は絵手紙も入ります。また、旅に出かけた時の印象に残ったところを、と対象は広がってきています。
今回までどのくらい描いてきたのか振り返ってみます。初回は新社会党中央総支部事務所です(左下カット)。2回目はろっこう医療生協・東雲診療所の組合員行事で中央区の静香園の観光茶園に茶摘みに行った時の親子の姿。3回目はポートライナーから神戸の街と山を望みました。4回目100号には布引ハーブ園。同園のグラスハウスにお陽様が当たり光り輝いてとても美しい風景でした。102号に描いたのは、診療所のサークル「歩く会」で出かけた布引の滝・雌滝。滝の水は少ないけれど紅葉がとても美しかったです。
07年に入ってまずは神戸太鼓が鳴り響き初詣に大勢が賑わう生田神社。2月、時々長女のところの孫の子守りに出かけていて、遊んだ後のお昼寝の寝顔がとても可愛く、つい描きました。08年に入って10月・113号に絵手紙で秋の七草。飛んで10年、120号の新年号には県本部の並びにある四宮神社。一宮から八宮まで、港神戸守護神厄除八社を折々に描いてきました。3月・121号は、南あわじ市の瀬戸内海国立公園・灘黒岩水仙郷。水仙はもちろん、菜の花や梅の花も美しく、海のはるか遠くにぽっかりと浮かんでいるように見え、瀬戸内ならではの光景で、素晴らしく眺めたのを思い出します。4月・122号は臨港線廃止跡の桜並木遊歩道。JR灘駅南から芸術の館まで約1㎞の道のりの遊歩道ができました。10月・127号は布引貯水池。「歩く会」ではここまで歩いています。
11年に入って、134号の盆踊り。地域で毎年夏に地蔵盆を行っていますが、その一コマです。11月・135号では絵手紙で「実りの秋」。私の好きな果物、ぶどう、柿、りんご、みかん、栗、梨とカゴに山盛り。
飛んで14年、11月・157号は岡山県牛窓、「オリーブ園の丘より瀬戸内海を望む」。小さな島々を眺めているとふと故郷を思い出しました。旅先では郵便はがきに描いた風景を自分宛てに送るのですが、それをどこかに落として投函できなかったのが残念でした。
まだまだ続くのですが、これまで13年間にわたって84回描いてきたものを抜粋で紹介させてもらいました。この私のコーナーは私の生きる励みのひとつになっているので、今後も『中央区版』が続く限り、私のコーナーを続けさせてもらっていきます。
(純)
|













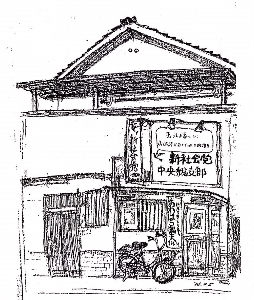 中央総支部では、支持者の方々とつながるため『新社会中央区版』を毎月発行していますが、その一角に「純子のスケッチブック」というコーナーをいただいています。2006年5月の97号から最新の11月・180号まで続いています。上手ではありませんが、絵を描くのは好きなので、私にとってはとてもうれしいものです。
中央総支部では、支持者の方々とつながるため『新社会中央区版』を毎月発行していますが、その一角に「純子のスケッチブック」というコーナーをいただいています。2006年5月の97号から最新の11月・180号まで続いています。上手ではありませんが、絵を描くのは好きなので、私にとってはとてもうれしいものです。