 「新社会兵庫」 4月28日号 「新社会兵庫」 4月28日号
- 大暴れの春は、駆け抜けた……。桜と雪と大風が過ぎ去ってみれば、早くも若葉がきらめいている。いきなりの初夏のような陽気の日もある。めまぐるしく日々が過ぎるからつい、忘れてしまうことが多いのだろうか。それでも、忘れ去ってはいけないことがやはりある▼統一自治体選挙が終わる。結果についてはさておいても、記録を更新し続ける低投票率は何としたことだろうか。私が子どもの頃、両親はすべての選挙に投票に出かけて行った。投票を終えて帰れば、誰に入れたかを問う子どもに教えてくれた。その答えは「働く者は社会党や」であった▼両親のような、いわゆる活動家でも何でもない普通の労働者をして「働く者は社会党」と言わせたものは何であったろう。賃金等労働条件の向上を求めることは当然であろう。同時に、青春時代に戦争をまともに体験した庶民にとって、これからは憲法を活かして人権・平和を守ろうという当時の社会党に希望を見出したのではないだろうか。少なくとも政治は関わるべき存在であった▼働き暮らす庶民の人権をないがしろにする政権にブレーキがない時、かつて武力の前に沈黙したことを忘れてはならない。二度と再び繰り返させてはならない。

- 憲法9条を覆す「戦争法」も、ガイドライン改定もいらない
-
2015年度予算が成立した。後半国会の最重要法案は戦争法案である。
政府と自民、公明両党は4月14日から協議を再開し、法案づくりの最終調整に入っている。5月連休明けにも閣議決定し、国会提出する。
■切れ目のない「日米軍事協力」
まず、戦争法案づくりと一体である日米軍事協力のための指針(ガイドライン)の再改定に触れておきたい。
「米軍と自衛隊が切れ目なく行動する機会が増える。アジア太平洋、世界中で対応することがこれで可能になる」(朝日)
4月8日の日米防衛相会談後の共同記者会見におけるカーター米国防長官の発言である。ガイドラインの再改定や戦争法制定のねらいを正直に語っている。
会談では、ガイドラインの再改定で「『切れ目のない日米協力』と日米同盟の『グローバル(世界規模)な性質』を盛り込むことで一致した」(毎日)。カーター米国防長官の言う通り、再改定は、世界に発生するどんな事態にも「切れ目」なく、地理的な制約もなしに「世界中」で米軍と自衛隊の軍事協力を取り決めることになる。外務・防衛担当閣僚会議(2プラス2)を、今月27日にニューヨークで開き、正式合意の予定になっている。
日米軍事協力関係を地球規模に拡大することは、日米安保条約の逸脱であり、日米同盟の質的転換である。そうであるにもかかわらず、ガイドラインは両政府の政策目標であるとして、安倍内閣は条約のように国会の批准は必要ないとしている。さらに重大なことは、安保関連法案(戦争法案)の国会論議を行わないまま、自衛隊と米軍の協力のあり方と役割分担を決めようとしている。先にガイドラインを決め、後から法案を論議するのは順序が逆である。安倍内閣の対米従属と国会軽視の政治姿勢は危険な段階に入っている。
■切れ目のない「戦争への道」
自民、公明が合意した安保法制(戦争法制)の骨格は、自衛隊法や武力攻撃事態法、周辺事態法など現行法の改定と新法の制定(恒久法)からなっている。昨年7月の閣議決定の内容も含め、「海外で戦争する国」づくりの法案が作成される。
その重大な問題点は、「武力行使の新3要件」に基づき、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本が攻撃されていなくても日本の存立が脅かされる危険がある「新事態(名称未定)」では、自衛隊による武力行使を認め、他国を防衛する集団的自衛権の行使を可能としていることである。「新事態」を自衛隊法と武力攻撃事態法に盛り込み、集団的自衛権の行使を法制化する。
集団的自衛権を発動する「新事態」であるかどうかの判断を行うのは時の政権であり、海外での武力行使の範囲が際限なく広がる。安倍首相は、米国が先制攻撃をした違法な戦争であっても、国会答弁で集団的自衛権の発動を否定していない。
次の問題点は、周辺事態法の改定や恒久法の新設によって、米軍や米軍以外の他国軍の戦争への後方支援(軍事支援)が歯止めなく拡大することである。
周辺事態法は、朝鮮半島など「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」に際し、自衛隊が米軍に軍事支援を行う根拠法である。この周辺事態法から「我が国周辺の地域」という地理的制約を外し、自衛隊の派兵地域を広げ、米軍以外の他国軍への支援も可能とする(地理的制約を外したため法律の名称も変わる)。また、周辺事態法から「後方地域」の概念を取り払って戦闘地域への派兵も可能とする。
後方支援の本丸は、新設される恒久法である。これまでテロ特措法やイラク特措法など自衛隊の派兵に合わせて時限立法の特措法で対処してきた。特措法では国会審議に時間を要し、機動的な対処ができないことから、政府の判断で、いつでも、どこでも、どんな戦争にも自衛隊を海外派兵する恒久法を新設する。自衛隊の活動範囲を制約してきた「非戦闘地域」の概念を取り払い、戦闘地域への派兵も可能にする。イラク特措法などでは「戦闘地域に行かない」という歯止めがあった。歯止めを外せば自衛隊への危険性は格段に高くなる。日本は敵国となり、「殺し、殺される」危険が現実のものとなってくる。
さらに、PKO協力法の改定によって、武器使用権限を拡大し、国連が統括しない人道復興支援活動や治安維持活動にも参加する。治安維持活動など任務の拡大で自衛隊が戦闘にまきこまれる可能性が高まる。
戦後70年、日本は一度も海外で武力行使しなかった。憲法9条を根底からくつがえし、立憲主義に違反する「戦争法」も、ガイドライン改定もいらない。
(4月13日記)
中西裕三(新社会党兵庫県本部元書記長)

- 丸山眞男のこと
-
去年、NHK教育テレビで丸山眞男を特集する番組が放映された。私が尊敬する石田雄氏が出演されていた。一方で江田五月氏(民主党参院議員)、山口二郎氏(法政大教授)、佐々木毅氏(東大元総長)も出演していて、私は嫌悪感を覚えた。なぜなら彼らは小選挙区制に賛成したからだ。彼らを許してはならない。
2014年は丸山眞男生誕100周年の年であった。丸山眞男は、私が最も尊敬する知識人であり、戦後の知を代表する人物と言っても過言ではない。私が丸山の名前を知ったのは大学に入ってからである。
丸山眞男の経歴について簡単に触れる。東京帝大法学部出身であり、戦後、東大総長を務め、全面講和論を主張し、吉田茂に「曲学阿世の徒」と批判された南原繁門下の政治学研究者である。戦時中に東京帝大法学部助教授でありながら、徴兵され、広島で被爆する。1946年に、雑誌『世界』で「超国家主義の論理と心理」を発表。論壇政治学の寵児となる。戦後は「丸山眞男」とともに始まったと言ってもよい。
政治学者に「あなたが尊敬する政治学者は?」と聞くと、一番多い答が「丸山眞男」である。だが、私が彼らに聞きたいのは本当に丸山眞男を尊敬しているのかということなのである。
丸山は一高生の時代から兵士として敗戦を迎えるまで、ファシズムの時代を経験した。丸山も悔恨共同体(戦争を止めることが出来なかったことに対して反省している人々のこと)の一員であった。
『科学としての政治学―その回顧と展望―』で、丸山は「政治学が特定の政治勢力の奴婢たるべきでない」と書いている。学問は真理の探究であり、自民党であれ、共産党であれ、学問が政治の「道具」になってはならない。
一方で丸山は、「一切の世界観的政治闘争に対して単なる傍観者を以て任ずる者は、それだけで既に政治の科学者としての無資格を表明しているのである」と書いている。
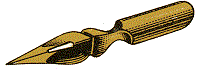 山口二郎氏は政治学者でありながら、民主党の候補者を応援するほど活動的である。「政治学者」という皮をかぶった「政治活動家」と言ってもよい。私は嫌悪感を覚える。しかしながら、山口氏が安倍内閣批判の論陣を張っていることについてだけ、私は擁護したいのである。
山口二郎氏は政治学者でありながら、民主党の候補者を応援するほど活動的である。「政治学者」という皮をかぶった「政治活動家」と言ってもよい。私は嫌悪感を覚える。しかしながら、山口氏が安倍内閣批判の論陣を張っていることについてだけ、私は擁護したいのである。
今の政治状況を見てみると、戦後民主主義の危機といってもよい。にもかかわらず、多数の政治学者が傍観者的態度をとっていることに対して、私は怒りを覚えるのである。
最後に、丸山は『現代政治の思想と行動』の後記で、「大日本帝国の『実在』よりも戦後民主主義という『虚妄』に賭ける」と書いた。今の私ならこう書く。「安倍自民党という『実在』よりも戦後民主主義という『虚妄』に賭ける」。
この言葉は、思想と哲学における私のアンガージュマン(社会参加)宣言なのである。
北場 逸人(22歳・学生)

- 3年で7人目の校長、代理人も辞任の学校
-
尼崎にある学校法人重里学園が経営する環境学園専門学校で2011年年末に武庫川ユニオンの分会が結成された。直接の経緯は、専任講師の2人が解雇を通告されたことであった(その後、他の組合員の1人にも解雇通告)。職場の不透明な経理も分会結成の動機であった。学生から授業料以外に実験費名目で徴収されているのに実際に使われる実験費がほんの一部でしかないなど、不透明な学校運営の民主化も要求に掲げた。
解雇問題は一旦解決したが、その後、教師から事務職への強制配転が強行され、現在、大阪地裁と大阪府労働委員会で不当労働行為であると地位の確認を求めて係争中だ。
環境学園専門学校は理事長の専制支配の学校で、とにかく教職員の入れ替わりの激しい学校である。大阪府労働委員会でユニオン書記長の私が証言したが、組合結成から4年目になるが、4月からは7人目の校長が就任。労務担当も4人替わり、現在は不在。事務職員は昨年末で全員が退職という始末である。労働委員会での元校長の証言で明らかになったが、2012年3月末で本当は専任講師5人全員を解雇することを決定していたというのである。理由は、入学する生徒が減少したから。このように堂々と証言した。理事長の言うことが絶対であるという職場状況である。
会社側の代理人2人がなぜか労働委員会の証人尋問後に辞任をした。なにが起こっているのだろうか。ここまで人が替わってしまい、替わらないのはユニオンの組合員だけである。教育機関としてまともにしたいと理事長の専制支配と闘い続けている。
大阪桐蔭学園が教材費などの裏金問題で揺れ動いているが、環境学園専門学校でも学園の不透明なお金の流れを指摘し、兵庫県や大阪府、土地を無償貸与している尼崎市に情報提供し改善に向けた指導を求め続けている。働く者の権利と学生たちの学ぶ権利は一体のものであることが明らかである。長い闘いとなっているが、組合員たちは諦めず粘り強く闘い続けている。正義の闘いにご支援を。
小西純一郎(武庫川ユニオン書記長)
|












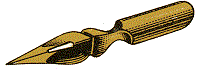 山口二郎氏は政治学者でありながら、民主党の候補者を応援するほど活動的である。「政治学者」という皮をかぶった「政治活動家」と言ってもよい。私は嫌悪感を覚える。しかしながら、山口氏が安倍内閣批判の論陣を張っていることについてだけ、私は擁護したいのである。
山口二郎氏は政治学者でありながら、民主党の候補者を応援するほど活動的である。「政治学者」という皮をかぶった「政治活動家」と言ってもよい。私は嫌悪感を覚える。しかしながら、山口氏が安倍内閣批判の論陣を張っていることについてだけ、私は擁護したいのである。